フグといえば、冬の味覚の代表格として名高い高級魚。
多くの人が知っている通り、フグは海に生息する魚だ。
だが、漢字で表記すると「河豚(ふぐ)」――どうにも“違和感”を覚えたことはないだろうか。
なぜ、海の魚に「河」という文字が? そこには、フグの歴史と、言葉の意外な背景が潜んでいる。
【第1章】「河豚」の正体──ルーツは中国の川にいた
そもそも「河豚」という漢字は、日本独自のものではなく、古代中国から伝わったもの。
その中国では、海ではなく“川に棲むフグ”が一般的だったのだ。
特に知られているのが「メフグ」と呼ばれる淡水性のフグ。
この種が、中国の河川や湖沼に多く生息し、人々の食文化にも根付いていた。
そのため、フグには「河」という文字があてられたというわけだ。
【第2章】「豚」の由来──鳴き声と膨らむ姿がヒント
もう一つ、気になるのが「豚」という文字。
なぜ魚に“ブタ”の字を使うのか?
実は、フグが危険を察知して膨らむ際、ブーブーという鳴き声を発する。
その独特な音と、丸々とした膨れ具合が“豚”を連想させたといわれている。
古代の人々は、その見た目と音からユーモラスなネーミングを生み出したのだ。
【第3章】日本のフグと「河豚」のズレ──海と川の誤解
ところが、日本で一般的に流通するフグの多くは海水魚。
ふぐ刺し、ふぐ鍋、唐揚げ…冬の味覚として親しまれるフグの大半が、海に棲む種類である。
ここで、違和感が生まれる。
・海の魚なのに「河」
・日本人の生活実感とズレる漢字表記
実際、「海豚」と書き換えた方が自然では…という声もあったという。
【第4章】「海豚」はすでにイルカだった
だが、その選択肢は封じられていた。
なぜなら「海豚」という表記は、すでに“イルカ”を指す言葉として定着していたからだ。
イルカも海に棲み、丸みを帯びた体と可愛らしい鳴き声を持つ。
そのため「海のブタ」=イルカという表現が、古くから日本語に根づいていた。
結果として、フグは「河豚」のまま残されたのである。
【まとめ】言葉のズレが教えてくれる、文化の面白さ
フグは海に生息する。
だが「河豚」という漢字は、中国から伝わった川のフグがルーツ。
日本と中国、文化の違い、歴史のズレ、そして、言葉の面白さ――。
普段何気なく使っている漢字の中にも、そんな“知られざる背景”が隠れている。
次にフグを食べるとき、そんな話を肴にするのも、粋な楽しみ方かもしれない。

「オイラは“豚”だけど、フグはちょっと食べたくなっちゃうブー…でも高級すぎるブー!」




















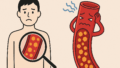

コメント