
「“名は体を表す”って言うけど、“読み”はもっと奥が深いブーよ…
第一章:2025年5月26日──戸籍に“フリガナ”が載る革命
2025年5月26日。日本の「名前」にまつわる大きな変化が静かに始まった。
改正戸籍法の施行によって、すべての戸籍に氏名の読み(フリガナ)が記載されることになった。
戸籍はこれまで「氏名」や「本籍」「筆頭者」などが記載された家族単位の公的記録。そこに「読み方」が加わることで、戸籍は単なる漢字の記録ではなく、“音”という新たな情報領域までも国家が管理することになる。

「これはただの制度変更じゃなく、“名乗る自由”と“呼ぶための正確さ”がぶつかる社会変化なんだブー!」
第二章:「良子」はヨシコ?リョウコ?──これまでのグレー運用
たとえば「良子」という名前があったとしよう。この漢字を、あなたは何と読むだろうか?
- ヨシコ?
- リョウコ?
- ハルコ?
- タダコ?
実はこれまで、政府は「どれが正解か」を把握していなかった。なぜなら、戸籍にはフリガナの届け出義務がなかったからである。
本人が役所に名乗ればそれが「その時点の読み」として使われたが、気分やライフスタイルの変化で「ヨシコ→リョウコ」に読みを変えても、基本的に国は関知しなかった。
問題にならなかったのは、「読み」が実務的にそこまで求められてこなかったからでもある。
第三章:背景には“キラキラネーム社会”の進行
ここでいくつか、現代的な実例を挙げてみよう。
- 光宙(ぴかちゅう)
- 黄熊(ぷう)
- 心愛(ここあ/しあ/ここな)
- 希星(きらら/きせい/のあ)
- 今鹿(なうしか)
- 七音(どれみ/ななお)
- 夢希(ないき/ゆめき)
読みの自由度が過剰に広がったことで、役所・学校・病院など、名前を扱うあらゆる現場で混乱が頻発するようになった。
- 健診の呼び出しで名前を間違えられる
- テストや通知表の入力ミスが続出
- 病院で読み違いにより別人の処置を受けかけたケースまで

「“名前”はその子の物語だけど、“読み”は社会が正しく読めるための鍵でもあるブー!」
第四章:何が変わるの?──“音”が制度に縛られる社会
では、改正後の社会で私たちはどのように“名乗る”ことになるのか?
【主な変更点】
- 戸籍に「読み」の届け出が義務化
- 間違いの修正には「読み訂正届」が必要
- 大きな変更には原則として家庭裁判所の許可が必要
つまり、これまでのように気分で「ヨシコ→リョウコ」へ読みを変更することは、原則として不可能になる。
一方で、「この人をこう呼ぶ」という共通認識を社会が持てるようになるという安定も得られる。
第五章:その読み、“政府の勘違い”かも?
政府は全国民に対し、「氏名の読みを記した確認通知ハガキ」を順次発送している。
だが、そこに記載されている読み方は──“政府の推定”である。
行政記録や一般的な読み方に基づき、機械的にフリガナを割り出して通知されるため、
そんな事態も十分に起こりうる。
間違っていた場合は、「読み訂正届」を提出することで修正可能。マイナポータルなどを活用したオンライン対応も一部で検討されている。

「それ、わたしじゃないブー…って思ったら、ちゃんと名乗り直しするブー!」
第六章:“読み”とは、誰のものか?
“名前”とは自己認識であり、“読み”は他者との接点。
声に出して読まれること=社会に向けて“自分を提示する”ことでもある。
国家がその響きを把握し、制度に記録するということは、“わたしの“音”そのもの”が制度に取り込まれるということだ。
おわりに:“呼ばれること”の意味を、いま一度考える
この改正は、ただの事務的な制度整備ではない。
それは、他人にどう読まれるかという“存在の形”を問うものであり、一方で国家に“名前の音”までも預けるという、新しい公共感覚の始まりでもある。
読みは、ただの読みではない。それは、自分をどう世界に提示するかという、名乗りの哲学だ。
※注釈
本記事では、改正戸籍法における「読み」の記録化をめぐって、キラキラネームを含む社会的背景を俯瞰的に扱っています。制度の詳細や手続きについては自治体ごとに異なる場合もあります。正式な確認は各市区町村窓口まで。

「君はどう呼ばれたいブー? そして、誰に呼ばれたいブー?」



















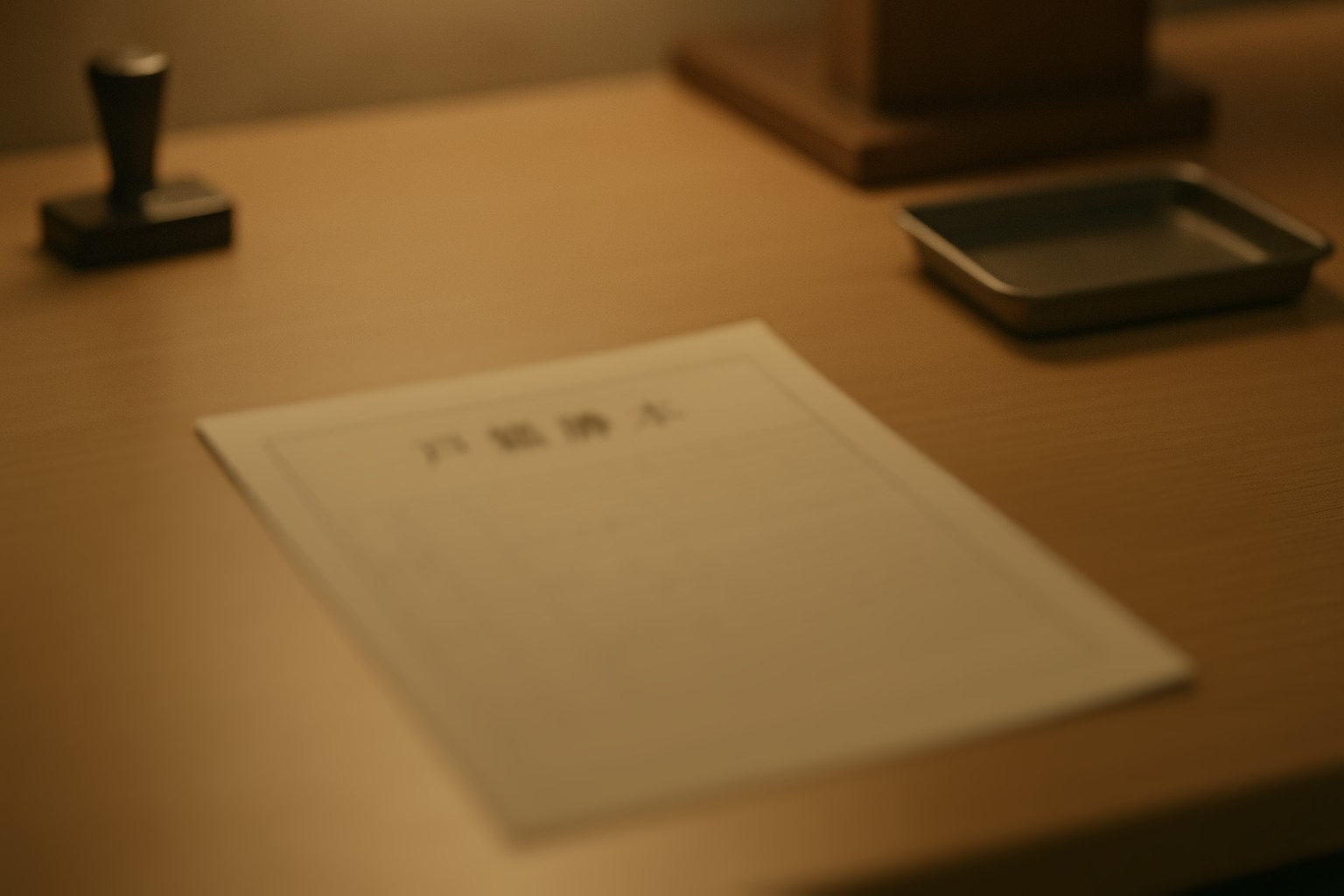


コメント