「頭が痛い」「身体がだるい」「でも今日は頑張らなきゃ」 ──そんなとき、つい手が伸びるのが解熱鎮痛剤。
イブプロフェン、アセトアミノフェン、ロキソニン…
これらの薬を飲むと、痛みが和らぐだけでなく「不思議と疲れも吹き飛んだ気がする」。そんな感覚を覚えたことはありませんか?
しかし、その“回復感”の正体は、実は「疲れを消している」のではなく「身体の悲鳴を黙らせている」にすぎません。
本記事では、解熱鎮痛剤が「疲れ」に効く理由と、その裏に潜む身体へのリスクを徹底解説。
「痛み止めで頑張る自分」に、どんな代償が待っているのか──
いま一度、立ち止まって考えてみましょう。
第1章:疲れが取れた“気がする”のはなぜか
解熱鎮痛剤には大きく2種類あります。
- イブプロフェン・ロキソニン(ロキソプロフェン)などのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)
- アセトアミノフェン
これらは、脳内で痛みや熱、そして炎症性物質の働きを抑える作用を持っています。
つまり、身体が「疲れた」「もう無理だ」と訴えている炎症のシグナルをシャットダウンしてしまうのです。
そのため、
「あれ?なんか元気になったかも?」
と錯覚するわけですね。
でも──
「治ったわけではない」。
単に痛みや疲労感を感じなくなっただけなのです。
第2章:身体に潜む“隠れたリスク”
では、その代償とは何か?
NSAIDsは胃の粘膜を守る働きを低下させ、胃痛・胃潰瘍・消化管出血のリスクを高めます。
アセトアミノフェンは肝臓で代謝されるため、過剰摂取は肝機能障害や肝不全の原因に。
NSAIDsの長期使用は腎機能障害や高血圧・心疾患のリスクも指摘されています。
一部の研究では、アセトアミノフェンの長期服用が血液がんのリスクを高める可能性も示唆されています。
第3章:乱用すると、どうなる?
「疲れたら痛み止め」が習慣化すると──
- 本来の身体の悲鳴に気づけない
- 無理を重ねることで知らないうちに身体がボロボロ
- 最悪、胃潰瘍・肝不全・腎不全という深刻な事態に
まさに「モグラたたき」。症状は消えても、根本は何も解決していないのです。
第4章:賢く、痛み止めと付き合う方法
- 用法・用量を守る
- 痛みや発熱のときだけ使う。疲労感だけでは飲まない
- 2週間以上続く不調は必ず医師に相談
- アルコールや他の薬との併用に注意
- 疲労回復は睡眠・栄養・休養・運動が基本
第5章:疲れの「根本改善」を忘れるな
薬で「今日だけ」頑張ることは時に必要かもしれません。
でも、繰り返せば「未来の自分」からツケを請求される。

「ブーッ!痛み止めは魔法じゃないブー!体を大事にするブー!睡眠とごはんも忘れないブー!」
健康は、消耗品ではなく投資。
薬を飲む前に、自分に問いかけてみましょう。




















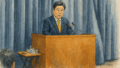
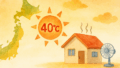
コメント