「1日って、24時間じゃないの?」
──その“当たり前”が、いま静かに揺らいでいます。
2025年7月10日、地球は24時間より1.38ミリ秒短く自転を終えました。
わずかな誤差に見えるが、これは人類史上における最も短い1日のひとつ。
そして近く、私たちはかつて経験したことのない“マイナスのうるう秒”という試練に直面するかもしれません。
原因は──地球の自転速度が加速しているからです。
潮汐、大気、地球内部の変化、さらには温暖化による氷の融解までもが複雑に絡み合い、
“1日”という概念そのものが、自然の気まぐれと人間の技術の綱引きの中に置かれ始めています。
これは、天文学や物理学の話にとどまらない。
GPS、金融システム、コンピューター、通信ネットワーク──
すべてが「1秒のズレ」によって揺さぶられかねない時代に、私たちは生きているのです。
時間は絶対ではない──それを最も痛感するのは、”今この時代”かもしれない。
第1章:地球の“スピード違反”──わずか1ミリ秒の衝撃
「えっ、地球の自転が速くなってるって?…それって何が問題なの?」
そう感じた方も多いはず。実際、2025年7月10日は観測史上もっとも短い1日となり、24時間よりも1.38ミリ秒短かったという報告がありました。
これまでの人類史ではほとんど意識されなかった“1日の長さ”が、いま世界中の天文学者や物理学者たちをざわつかせているのです。
そして、2029年までに初の「マイナスうるう秒」が導入される可能性が──。

「1日が短くなったって、寝坊した言い訳にはならないブー!」
第2章:「原子時計」とは何か──人類が創った“絶対時間”
この問題の背景には、「時間とは何か?」という本質的な問いがあります。
1955年、世界は“原子の振動”を基にした「原子時計」を導入。これによって時間の計測精度が飛躍的に高まり、地球の自転とは無関係な「絶対的な時間」が誕生したのです。
この“絶対時間”(協定世界時UTC)と、“地球が1回転する自然なサイクル”(天文時)とのズレを補うために誕生したのがうるう秒。
- 1972年〜現在までに27回追加(すべて“プラス”)
- 地球の自転が遅れたとき、1秒追加して帳尻合わせ
- 通常は約1.5年に1度のペース
ところが今、状況が逆転し始めたのです──
自転が“速く”なってしまった。
第3章:なぜ速くなった?──自然のリズムと大気の揺らぎ
地球の自転速度を変化させる要因は極めて複雑かつ多層的。
その主な要因は以下のとおりです。
■ 主な自転速度変化の原因
月が赤道近くにあると遅く、極地近くにあると速くなる。
夏になると大気の回転速度が鈍る → 地球本体が補って加速。
液体核が遅くなった分、外殻(固体)が速まって補っている可能性。
地球とその大気・内部構造は角運動量を共有する“連動システム”。
どこかがブレると、別のどこかが補う──。これが“物理の法則”なんです。
第4章:気候変動の“意外な役割”──氷が溶けると自転は遅くなる?
ここで少し意外な話を──
「地球温暖化」は多くの悪影響をもたらしていますが、“自転の加速”に対してはブレーキとして働いている側面もあります。
- 南極・グリーンランドの氷が溶ける
↓ - 水が赤道付近に分布
↓ - 自転速度が“遅くなる”傾向(スケーターが手を広げる理屈)
つまり、もし氷が溶けていなかったら…
すでにマイナスうるう秒が適用されていた可能性すらあるというのです。

「氷が溶けると“地球が回るスピード”まで変わるなんて…想像超えてるブー!」
第5章:「マイナスうるう秒」は現代文明の試練?
さて、ここで問題となるのが“初のマイナスうるう秒”。
- 原子時計の方が“長く”なりすぎた → 天文時とズレる
- ズレを「マイナス1秒」で調整
- しかし、これまで一度も実施されたことがない
この「マイナスの1秒」がなぜ恐れられているのか?
- ソフトウェアやOSが時間は常に“増える”と想定して設計されている
- タイマーやログ、スケジューラーに“1秒逆戻り”は想定外
- 2012年にはLinuxシステムが“プラスのうるう秒”で不具合
つまり、未経験の時間操作がシステム障害を引き起こす危険性があるのです。
第6章:「1日が短い」は誰の問題か?──未来社会と“時”の哲学
目の瞬きは100〜400ミリ秒。
地球の自転短縮は、たった1〜2ミリ秒。
──私たちの日常にはまったく影響がない…ように思える。
でも実は、
・人工衛星の軌道修正
・GPSシステムの正確性
・金融市場の高頻度取引のタイミング
など、高度に“時間”に依存した社会の基盤が揺らぎかねないのです。

「時間は“空気”みたいなものだブー。でも、それが狂ったら人類は息できなくなるブー!」
まとめ:地球は回り続ける──でも“時間”は人間が作ったルール
地球の自転速度は、太古から揺らぎ続けてきました。
恐竜時代は1日21時間、7000万年前は23.5時間。
そしていま、1日の長さがミリ秒単位で変化している。
でも、それに対応できるかどうかは、人間側の“文明”の問題なのです。
- “1秒”の変化が、グローバルシステムに打撃を与える時代
- 温暖化が“地球の回転”を左右する、壮大なバタフライ効果
- 「マイナスうるう秒」は、未来の技術信頼性を問う“試金石”
たとえ太陽が昇り、沈む毎日であっても──
その“1日”が、これまでと同じとは限らない。
地球は回り続ける。
けれど、「時間」だけは、人間の手で守らねばならない。

「明日も“24時間”あると信じてる人たちに届けたい記事だブー!」




















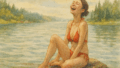
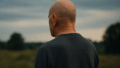
コメント