ラスクと聞いて、真っ先に思い浮かぶのは──
高崎から届く、青・白・赤のリボンが映える上品なパッケージ。
「ガトーフェスタ ハラダ」。
洋菓子の宮殿のような本社工場。
どんな年代にも愛される「グーテ・デ・ロワ」。
その一枚には、100年以上の歴史と、
“幸福の創造”という企業哲学が込められていた。
第1章:始まりは和菓子店だった──1901年、群馬県にて
ラスクで全国に名を馳せたハラダの原点は、なんと和菓子屋だった。
明治34年(1901年)、群馬県新町で創業した「御菓子司原田」。
初代・原田丑太郎が語ったとされる言葉──
「菓子屋は、美味しくなければだめ。材料にお金を惜しまないように」
──この思想が、のちの「ハラダのラスク」の核心を形づくることになる。
第2章:戦後の苦難と、パン屋への転換
戦争により、砂糖が手に入らなくなった。
正規ルートで材料が揃わない以上、和菓子屋としての継続は困難。
そこで、家業は配給パンの製造販売へと方向転換。
当時、家業を継いだのが俊一氏。彼は医者志望だったが、
一家の生活と弟たちの学費のため、パン屋としての道を選ぶことになる。
そしてここから、「ラスク」の原点が生まれていく。
第3章:「余ったパン」からの発想──ラスク誕生のきっかけ
パンが売れ残る。
固くなってしまい、廃棄するしかない。
──そんな状況の中、俊一氏が頼ったのは、
かつてパン技術を学んだ大阪の恩師・雁瀬大二郎先生。
「ラスクがいい」
この一言が、その後のガトーフェスタ ハラダを決定づけた。
最初は、余剰パンの再利用。
だが、それがやがて、主役の座へと変貌していく。

「もったいないから始まったのに、ブランドの顔になるなんてドラマチックだブー!」
第4章:「王様のおやつ」誕生──パッケージにも込められたメッセージ
2000年、「グーテ・デ・ロワ(=王様のおやつ)」が誕生。
フランスパン仕立てのラスクは、贈り物文化と相まって大ヒットを記録。
特筆すべきは、青・白・赤のトリコロールデザイン。
- “王室風”で高級感のある配色
- 一目で「ハラダ」とわかるブランド力
- 贈り物に選ばれる、華やかで気品ある存在感
このビジュアルは、商品そのものをギフトの象徴へと昇華させた。
第5章:「作ったものはすべて売り切る」──サステナブル経営の実践
ガトーフェスタ ハラダの誇り──
完成品の廃棄率ほぼゼロ。
- 店舗ごとの販売実績をリアルタイムで集計
- 過剰在庫を生まない仕組みを構築
- パン耳や副産物も飼料として再利用
その食品リサイクル率は98%。
日本の製造業平均(95%)を上回る数値だ。
「無理に店に押し込むことはしない。売れた分だけ作る」
──生産本部長・上田氏の言葉
第6章:なぜ量販店で売らないのか?──20年後、30年後のブランドを見据えて
いまもなお、ハラダのラスクはスーパーやコンビニでは買えない。
なぜか?
節子専務の言葉に、企業哲学が凝縮されている。
「一気に流通すれば、その商品の寿命が短くなる。
わたしたちは20年後、30年後にブランドが輝き続けることを見ている」
ブランドとは、急成長させるものではなく、守り育てていくもの。
その姿勢が、消費者の信頼を着実に積み上げてきた。
第7章:「幸福の創造」──ラスクの先にあるもの
俊一会長が語る信条は明快だった。
「お客様に幸福感を味わっていただきたい」
「私の言葉で言うなら“幸福の創造”です」
その理念は、製造、品質管理、パッケージ、文化事業──
すべてに息づいている。
定例コンサート、展覧会、メセナ活動。
ハラダのラスクは、お菓子を超えて“文化”になっているのだ。
終章:トリコロールの先にある、“日本の誇り”
もともとは、売れ残りをどうにかしたいという思いから始まったラスク。
今や「ハラダ」と聞けば、誰もが思い浮かべる“贈り物の代名詞”。
その背景には──
- 「質のいいものを、誠実に作り、きちんと売り切る」姿勢
- ブランドを育てるという長期視点
- 食文化と芸術をつなぐ哲学的なビジョン
が脈々と流れている。
ラスクという日常的な一品の中に、
ここまで深く、真摯な物語が隠れているとは──
まさに、日本が誇る洋菓子ブランドである。
- 元は和菓子屋だったハラダが、パン屋を経てラスクの巨星に
- ラスクは“売れ残り救済”から始まり、“贈り物の主役”へ
- 廃棄ゼロのサステナブル経営がブランドの裏支え

一気に売らず、長く愛されることを見据える“美学”がここにあるブー!




















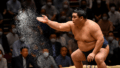

コメント