山梨県を代表する銘菓といえば──多くの人がこう答えるだろう。
「桔梗信玄餅(ききょうしんげんもち)」
ピンクや赤、紫の小さな風呂敷に包まれたその姿は、まるで小さな宝物のよう。
お餅、きな粉、黒蜜の三位一体が生むあの味わいもさることながら、「包み方」に心を奪われる人も多いのではないだろうか。
だがその風呂敷スタイル──実は、お金がなかったから生まれたものだと聞いたら、きっとあなたも驚くことだろう。
◆「機械が買えなかった」からこそ生まれた、手包みの文化
1968年(昭和43年)、製造元である桔梗屋は、新しいお土産菓子の開発に取り組んでいた。
苦心の末、きな粉×お餅×黒蜜という黄金のレシピにたどり着く。
だが、ここで大きな壁にぶつかる。
完成した商品をパッケージするための「専用機械」を導入する予算がなかったのだ。
そこで、やむなくスタッフが1個ずつ風呂敷状の不織布フィルムで手包みすることに。
それが意外にも「日本的でかわいい」「上品」と大反響を呼び、結果的に大ヒットに繋がった。
現在でも、1日12万個を手包み!
包装スタッフは“6秒で1個”という職人技を誇るという。
◆風呂敷の中には「きな粉こぼし対策」という合理性も?
見た目の可愛さだけではない。
実は、包装そのものが“きな粉の受け皿”としての役割を果たしているのも特筆すべき点だ。
ご存知の通り、桔梗信玄餅の構造はこうだ。
- 容器に柔らかいお餅が3つ
- その上にたっぷりのきな粉
- 別添の黒蜜を後がけ
この構成、じつはとても“こぼれやすい”。
だからこそ、風呂敷状に包むことで、
- 食べる際に広げて敷物として使える
- 手が汚れない、机も汚さない
- 食後はそのまま包んでポイ
という実用性まで兼ね備えていたのだ。
可愛いだけじゃない。合理的でもあるのが桔梗信玄餅の真骨頂なのである。
- 包装はコスト削減の苦肉の策だった
- 結果的に大ヒットし、“名物化”
- 現在も1日12万個が職人技で手包み
- 見た目と実用性を両立した「美しい工夫」
◆「もみもみする」ってどういうこと?桔梗屋が推奨する裏技的食べ方
さて、あなたはどうやって桔梗信玄餅を食べているだろうか?
黒蜜を容器に直接かけて、そのままスプーンで食べる──。
それがスタンダードだろう。
だが、メーカー公式が「実はおすすめ」として紹介している裏ワザ的な食べ方が存在する。
その名も…
「風呂敷もみもみスタイル」
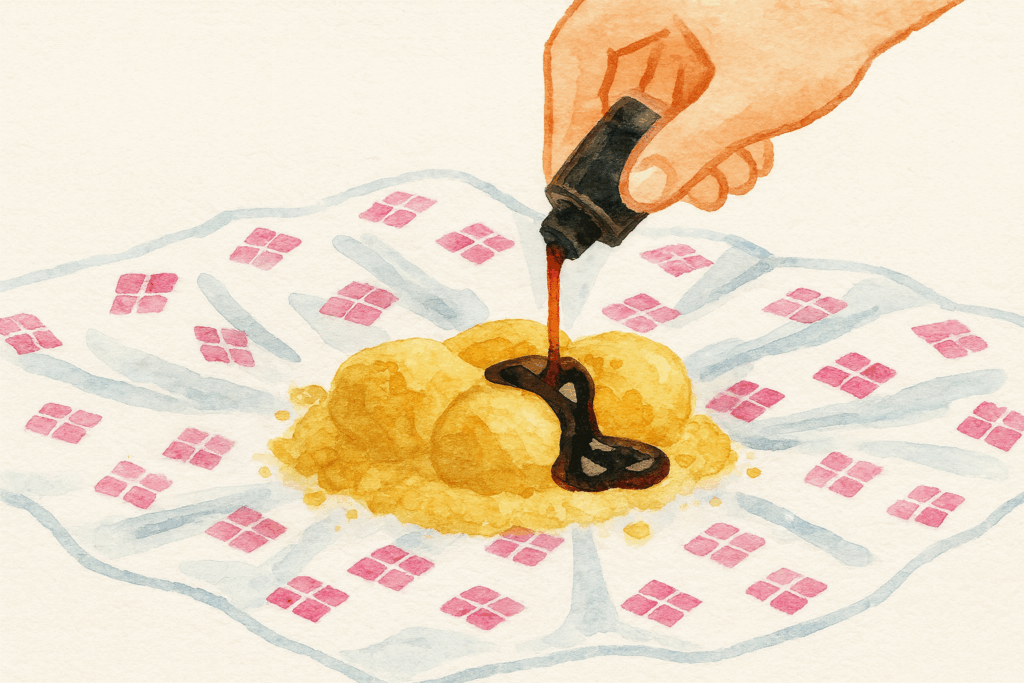

- 風呂敷を広げ、その上にお餅・きな粉・黒蜜すべてをぶちまける
- 風呂敷の四隅をまとめて袋状に包む
- やさしくもみもみ…
- 中でお餅ときな粉と黒蜜が一体化
- 完成!とろっとろの“味の塊”が誕生!
テレビでもたびたび紹介され、意外と多くの人が「一度やるとクセになる」というこの方法。
桔梗屋の公式サイトにも“番外編”として掲載されており、もはや準公式レベルの存在感である。
◆「信玄」の名の由来は…じつは関係ない?
最後に、このお菓子の名前──「信玄餅」。
多くの人が「武田信玄が好きだったお菓子」だと思っているかもしれない。
だが実際には、信玄公とこの餅に歴史的なつながりはない。
「山梨県の代表的な人物=武田信玄」
「山梨県の代表的なお土産になってほしい」
──そんな想いから命名された、“願いのネーミング”なのである。

「お金がなかったからこそ、生まれた美しさ…涙出るブー!
包装も味のうちって本当だったブー!次は“もみもみ”で食べてみるブー!」
◆“風呂敷の革命”が生んだお土産菓子の名品
桔梗信玄餅は、味だけではなく「手包み」というアナログな美学を今に伝える稀有な存在だ。
風呂敷という伝統と、お菓子という現代の幸福が絶妙なバランスで共存している。
そしてそこには、「足りないからこそ工夫する」という、どこか昭和的なものづくり精神も宿っている。
風呂敷に包まれた小さな餅には、たくさんの物語が詰まっていた──。






















コメント