「何回言ったら分かるの?」
「教えたよね?どうしてできないの?」
──そんな言葉を部下や後輩にかけたことはないだろうか。
でも実はそれ、教え方そのものに原因があるのかもしれない。
いま、「教える技術」に革命が起きている。
そのカギとなるのが、3つのスキルパターンに合わせた“育成戦略”だ。
この記事では、誰でも「教え上手」になれるエッセンスを、わかりやすく解説する!
第1章:「教えたのにできない」は教える側の責任
「言えばわかる」「見れば覚える」は、教える側の幻想に過ぎない。
たとえば…
- 覚えるまでに時間がかかる人
- 理解できるタイミングがバラバラな人
- 言語より体感で覚えるタイプの人
人にはそれぞれ学習のクセがあるのに、「一斉に」「同じように」教えるから、伸びない。
「できないのは、100%教える人の責任です」
この言葉は厳しいようで、実は“教える技術”を見直せば誰でも教え上手になれるという希望の裏返しだ。
第2章:「教える技術」は3つに分類できる
■ スキルのタイプで“教え方”は変えるべき
育成対象のスキルは、実は3つのパターンに分類できる。
パターン①:運動スキル(身体で覚える)
- 例:タッチタイピング、ピアノ演奏、道具の操作
- 特徴:体を動かす“慣れ”が必要
- 教え方のポイント:
- すぐに“実演”させる
- 回数をこなして覚えさせる
- 「できた」を体感させる
NG:「まず理論から教えよう」
OK:「見本を見せて、まずやらせる」
パターン②:認知スキル(頭で考える)
- 例:企画立案、文章作成、プレゼンテーション
- 特徴:情報を整理し、判断を伴う
- 教え方のポイント:
- モデルを提示(よい例・悪い例)
- 一緒に“考えるプロセス”を分解
- フィードバックを段階的に
NG:「やればわかるでしょ」
OK:「ここはこう考える理由があるんだよ」
パターン③:態度スキル(行動や習慣)
- 例:報連相の徹底、モチベ維持、計画的行動
- 特徴:意識やマインドが問われる
- 教え方のポイント:
- 行動を“習慣化”させる仕組みをつくる
- 成果や変化を“見える化”
- 「やる気」ではなく「やり続ける仕掛け」を設計
NG:「やる気が足りない」
OK:「できる自分」を実感できる工夫をする
- 何を教えているのか?スキルのタイプを分類
- どう教えるのか?タイプ別に手法を切り替える
- 成果が出ない?原因は“相手”ではなく“方法”にある
この3ステップで、教えることが「責め」ではなく「支援」になる。
第3章:「自分にも使える」教える技術の意外な応用
実はこの教え方、“自分育て”にも使える。
たとえば…
- タイピングを早くしたい → 運動スキル → 反復と体感練習
- ロジカルな文章を書きたい → 認知スキル → 型と添削
- 毎朝早く起きたい → 態度スキル → 習慣の設計
つまり、自分自身に対しても「正しい教え方」をすれば、変われるということ。

「ブクブーも「ちゃんと教えたのに!」って怒っちゃうことあるブー!
でも、それって「ブクブーの教え方」がズレてたってことかもしれないブー…
人を責める前に、自分の“伝え方”をアップデートするのがプロブー!」
結論:「教える力」は、最強の“育てる力”になる
教え方を変えれば、部下が育つ。
チームも、自分自身も、ラクになる。
そして何より──
“伝わった”という喜びは、教える側の人生も豊かにする。
「できない人」を変えるのではなく、
「できる教え方」に変わるだけ。
あなたも、“教え上手”になれる。今すぐ、はじめてみよう。




















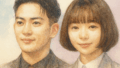
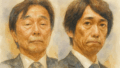
コメント