「預けたのに、訴えられる」──。
福井の介護施設で、認知症の高齢者が誤って洗剤を飲み、数日後に死亡。
遺族は施設を訴え、裁判所は2800万円の賠償を命じた。
「施設に落ち度があった」とする判決に、
ネットでは“そんなこと言ったら介護なんて成り立たない”と怒りが噴出している。
洗剤の誤飲と肺炎、責任の所在。
そして「認知症を預かる意味」の再定義──
この事件は、ただの事故や過失の話ではない。
介護現場に漂う“諦めのリアリズム”と、“制度の空洞”を突きつける問いなのだ。

「これが“失敗できない介護”なら、誰が続けられるんだブー……」
■ 事件の概要──「洗剤を飲んで死んだ」で済まされない話
2022年、ある85歳の認知症男性が介護施設で食器用洗剤を誤って飲み、
3日後に誤嚥性肺炎で亡くなった。
これに対し、福井地裁は2025年7月、施設側に約2800万円の支払いを命じた。
理由はこうだ。
- 男性は認知症が進行していた
- 施設は「水を飲むために洗面所へ行く習慣」を把握していた
- にもかかわらず、誤飲リスクのある洗剤を視認できる場所に置いた
──つまり、「誤飲の可能性を予見し得たのに、防がなかった」という判定である。
■ SNSと掲示板は騒然──「それならもう介護なんて無理」
この判決は即座にネット上で炎上した。
「どうやって防ぐんだよ、縛り付けるか?」
「洗剤置いたらアウト?じゃあ何も置けないじゃん」
「裁判長、介護現場知らなすぎる」
「むしろ訴えた遺族に洗剤代払ってほしい」
「これで2800万って……保険効かないの?」
──怒りと諦めと冷笑が入り混じったコメントが溢れた。

「みんな、つい“怒り”で反応しちゃうけど、そこにある“疲れ”の方が根深いブー……」
■ 介護の“現場と理屈”のすれ違い──「義務と現実」の板挟み
このケースは、ただの「不運な事故」では済まされない。
というのも、特別養護老人ホーム(特養)は「安全配慮義務」が特に重く課せられる法的位置付けだからだ。
しかし──
- 24時間ずっと付きっきりにはなれない
- 拘束すれば「人権侵害」になる
- “危険物”を排除しすぎれば、生活環境が機能しなくなる
これらの現場のジレンマを、法律は想定していない。
結果、「命を守るはずの制度が、誰も守らなくなる」構図が生まれつつある。
■ もう誰も引き受けたくない?「認知症お断り社会」の地鳴り
ネット上では、こうした声が飛び交った。
「もう認知症は引き取らん方がリスク少ない」
「認知症に関わると不幸になる」
「この判決で“認知症=訴訟リスク”が確定した」
「どうせ死ぬ老人を預かって、死んだら訴えられるの地獄でしょ」
「これ、老人を“金に換える”ライフハックでは?」
冷たく見えるかもしれないが、背景にあるのは「限界」のリアリティだ。
家でも見きれない。
施設に預けても、責任だけは残る。
その先に待つのは、「誰も引き受けなくなる社会」である。
■ “制度の失敗”を現場に押しつける時代は終わりにしないといけない
この事件が投げかけたのは、「どこまでが施設の責任か?」という問題だけではない。
「高齢社会をどう支えるか」のモデルそのものが、すでに破綻しかけていることを露呈させた。
すべての選択肢が疲弊と分断を生み出している。
それなのに、新しい制度の設計図は提示されていない──。
■ まとめ:「仕方なかった」が許されず、「仕方ないよね」も言えない時代
もちろん、命の重さは代替できない。
しかし同時に、完璧な介護もまた不可能だという事実から目を逸らしてはいけない。
「頑張ったけど、防げなかった」
そんな“現場の声”が、ちゃんと届く社会にしないと、
“誰も預けられず、誰も引き取れない”未来がすぐそこにある。

「介護は“正解のない仕事”だブー。それを“後出しの正義”で裁くなら、もう誰もやらなくなるブー……」




















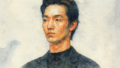
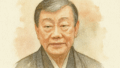
コメント