「なんか、学校で集めさせられてたよね…ベルマーク。」
そう語る大人は多い。
お菓子の袋をハサミで切って、家で集めて、小学校に持っていく──
でもあれって、いったい何だったのか?
ポイント?クーポン?景品交換?
違う。
ベルマークは、社会を動かす“仕組み”だった。
そしてそれは、いまも静かに、生き続けている。
この記事では、懐かしい記憶の奥に眠るあのベルマークの正体を、
教育支援・国際協力・地域貢献の観点から、やさしく紐解いていく。
「ただの紙切れ」じゃない。あれは、未来へのチケットだった──。
◆ 小学校時代の謎の義務──ベルマークとは何だったのか?
牛乳パック、袋入りお菓子、文房具の隅っこ──
どこかに「ベルマーク」が印刷されていたのを覚えていないだろうか。
そして、なぜか母親に言われて「切って集めて、学校に持っていく」
当時は「ポイントを貯めてなにか得するのかな?」と漠然と思っていたものの、
実際には何が起きていたのか、知っている大人は案外少ない。

「そういえば結局、なんだったんだよアレはブー!回収されてその後、どこ行ったか聞いた記憶ないブー!」
◆ ベルマークとは、「教育支援の仕組み」だった
ベルマークは、1960年に朝日新聞社が設立した「ベルマーク教育助成財団」の仕組み。
目的は「子どもたちに平等な教育の機会を」
発祥当初は、「黒板とチョークしかない地方校にも、ちゃんとした教材を」という思いから始まった。
今では28,000校以上の学校・団体が参加しているという大規模な活動だ。
◆ 「1点=1円」換算。ポイントではなく“学校の資金”になる
意外と知られていないが、
ベルマーク1点=1円として、学校の“預金”になる。
つまり、家庭で集めたベルマークを学校が送ることで、
- ボール
- 楽器
- 教材や備品
などを購入できるようになるのだ。
「家庭→学校→子どもたち」の教育投資回路、
それがベルマーク。
◆ ベルマーク運動の“6つの流れ”とは?
実際の運用フローは以下のとおり。
- 集める:家庭や地域からベルマークを回収
- 切る:マーク部分だけ切り取って分類
- 仕分け・計算:メーカーごとに分類して点数集計
- 送る:ベルマーク財団へまとめて送付
- 買い物:学校で必要な教材や設備を購入
- 支援:購入金の一部が、国内外の教育支援にも回される
ベルマークは日本の学校だけでなく、
開発途上国や被災地の子どもたちにも届いている。

「えっ、ベルマークって、“家庭でできる国際支援”でもあったのかブー!
これ、もっと知っておくべきことだったブー…!」
◆ 見返りはない。けれど“投資”である。
ベルマークに個人ポイントは存在しない。
使っても何ももらえない。Tポイントもdポイントもない。
でもその代わりに、
「見えない教育の恩返し」がちゃんと続いている。
「あの時ベルマークを集めてた小学生」が、
「いまベルマークで育った学校の先生」になっているかもしれない。

「回収箱に落とした1枚が、誰かの“未来”に届いてたんだブー…」
- ベルマークは“学校の資金源”になる社会的仕組み
- 個人ポイントではないが、教育への“見えない貯金”になる
- 活用されるのは教材や備品、さらに国内外の教育支援にも
- 実は全国28,000超の学校・団体が参加
- ただの紙切れではなく、支援の“種”だった!
◆ 最後にもう一度──ベルマークは、未来へのチケット
集めて、切って、送って。
地味で面倒。誰の得にもならない。
…ように思っていた。
でも、その紙切れ一枚が、
子どもたちに机を届ける。
体育館にボールを届ける。
世界のどこかに、学びを届ける。
ベルマークとは、「静かに届く応援」だったのだ。




















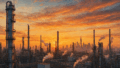

コメント