空から降ってくる「氷の球」。
それがただの氷じゃないと聞いたら、あなたは信じますか?
雨でも雪でもない、突如として地上に叩きつけられる「雹(ひょう)」。
その中身は、一見すると無機質な白い球体。
けれど、よく見てみると…そこにはある驚きの構造が隠れていました。
一体その中はどうなっているのか?
なぜ空からこんなものが降ってくるのか?
えっ、真夏に氷の粒?夏にも雹が降るのはなぜ?
そして──「輪切り」にして初めてわかる、自然の不思議なメカニズムとは?
“空から落ちてきた謎”を、今回はじっくり解剖してみます。
■ 雹(ひょう)ってそもそも何?あられとどう違う?
まず、冒頭で整理しておきたいのが「雹(ひょう)」と「あられ」の違い。
- ひょう(雹):直径5mm以上の氷の塊
- あられ(霰):直径5mm未満の氷粒
つまり、見た目のインパクトこそ似ていても、
雹は“空飛ぶ氷の弾丸”レベルであられとは別格の存在。
しかも、ひょうはただの凍った水滴ではありません。
その正体は──
“幾層にも重なった氷のレイヤー構造”なのです。
■ ひょうを輪切りにしてみたら…?
科学者が実際に雹を真っ二つに切ってみたところ、驚くべきものが現れます。

- 中心には最初の氷の核(ごく小さな氷粒)
- その周りを幾重にも取り囲む氷のリング状の層
断面は、まるで年輪のような模様。
1層ごとに微妙に色味や透明度が異なり──
半透明の輪切り模様が美しい…が、恐ろしい。
この層構造こそが、ひょうの“形成過程の履歴”そのもの。
■ 空の中で何が起きているのか?【積乱雲のジェットコースター】
雹ができるのは、いわゆる「入道雲=積乱雲」の中。
そこでは、
- 水滴が氷になるほどの超低温領域(氷点下20℃以下)が広がっている
- 強力な上昇気流(時に時速100km以上)が発生
- 凍った粒が上へ下へと何度も上昇・落下を繰り返す
つまり、
「天然のジェットコースター」に乗った氷の粒が、
空中で何度も水分をまとい→凍り→層を重ねる
というサイクルを繰り返して肥大化していく。
こうして形成されたレイヤーが、「輪切りにしたときの年輪模様」になるというわけです。
■ 雹の年輪が語る“空の記録”
実はこの「ひょうの輪切り」は、気象研究の貴重な証拠。
- 層の厚さ → 上昇気流の強さ
- 氷の透明度 → 凍るスピードや環境の違い
- 氷の混入物 → 汚染度、塵、花粉などの空中成分まで
まさに“空から落ちてくる履歴書”。
1粒の雹が、大気中の情報をまるごと記録しているんです。
■ 真夏に“氷の弾丸”?──雹はむしろ「夏の怪物」
「雹(ひょう)」というと、冬や寒い時期を連想しがちですが──
実はその多くは“夏”に降っているのです。
あの入道雲(積乱雲)の中では、
上空1万メートル以上に達することもあり、
−60℃以下の世界が広がっています。
地上は猛暑でも、雲の内部は冷凍庫どころか液体窒素クラス。
そしてそこに、強烈な上昇気流。
氷になった粒が何度も上下運動しながら成長し、
ついには“落ちきれなくなって”地上に叩きつけられる──
それが「雹」なのです。
- 地上の気温は無関係、雲の中が異常寒冷地帯
- 強烈な上昇気流=氷の成長エレベーター
- 夏はこの条件が最も揃いやすい

「夏空の“モコモコ”が、氷の粒を育ててたとは…
見上げた時点で、もうヤバかったんだブー!」
■ 雹が巨大化するとどうなる?
実は、世界最大級の雹の記録は…
- 直径20cm超え(ソフトボール大)
- 重さ約1kg超え(落下時は命に関わる)
アメリカや中国では、自動車のフロントガラスが粉砕されるレベルの“殺人ひょう”が毎年報告されています。
まとめ
たった1粒の氷が、空のなかで何度も浮かんだり落ちたりして、
その旅の記録を“層”として刻んでいく──。
輪切りにして初めて見えるその中身は、
気象の暴力性と、自然の造形美をあわせ持つ“空からの贈り物”だったのです。
- 輪切り=氷の年輪 → 何度も上昇/落下した証拠
- 層の厚みや透明度 → 気象の強度や変化を可視化
- 中心核 → たった一粒の塵から始まる氷の旅路

「ひょうってただの氷の塊じゃなかったブー!
“空を旅して成長した氷の履歴書”だなんてロマンだブー…」




















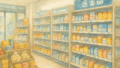
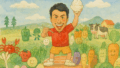
コメント