長崎の港町に忽然と現れたヨーロッパ。
チューリップが咲き乱れ、鐘楼が時を告げ、運河には白鳥が浮かぶ。
その街の名は「ハウステンボス」。しかしそれは、「House」ではない。
綴られた文字は Huis Ten Bosch──オランダ語で「森の家」。
実在する王宮にその名を借りたこの街は、単なる観光地ではない。
それは一人の男の“ふるさと再生の夢”から始まり、バブルという時代の熱狂に支えられ、そして一度潰えかけた後に、奇跡の復活を遂げた都市の物語である。
環境先進都市の実験場として。
光と花が咲き乱れるエンタメ王国として。
そして今、アジア屈指の未来型リゾートを目指して。
ハウステンボスは常に、変化し続ける“生きた街”であり続けている。
本稿では、ハウステンボスの誕生から経営破綻、復活、そして現在進行形の進化までを、
魂のこもった「街づくりの叙事詩」として、一章ずつ濃厚に描き出す。
第1部:歴史編──狂気と情熱が生んだ「理想の未来都市」
■1-1:創業者・神近義邦の夢と、汚された海
物語の出発点は、「レジャー」でも「儲け話」でもなかった。
ハウステンボスの創業者、神近義邦(かみちか よしくに)氏が目にしたのは、
ふるさと・大村湾の変わり果てた姿だった。
かつての豊かな海は、生活排水によって濁り、臭い、死んでいた。
高度経済成長の裏側で、日本中の水辺が失っていた“風景の記憶”。
神近氏は、その喪失に抗うように決意する。
「世界で最も美しい村を、この手で蘇らせる。」
単なる環境保全ではない。彼が目指したのは、文化と自然が共存する“理想郷”だった。
その答えを探し求めて訪れたヨーロッパで、彼が心を奪われたのがオランダである。
- 干拓で土地を広げた人類の英知
- 風車と運河が織りなす持続可能な町並み
- 王宮と市民の家が同じ空の下で息づく、美しき共存の文化
そして出会ったのが「Huis Ten Bosch(森の家)」。
王室が実際に暮らす宮殿の名は、神近氏にとって理想の都市そのものだった。
「これはテーマパークではない。自然と文化、そしてテクノロジーが融合した“未来の都市”だ。」
彼のビジョンは、やがて国をも動かすほどの巨大プロジェクトへと進化していく──。
■1-2:バブルの熱狂が生んだ「152万㎡のキャンバス」
1980年代後半、日本中がバブルに酔いしれていた時代。
この狂騒のエネルギーは、神近氏の「森の家」構想に奇跡的な追い風を吹かせる。
舞台は、東京ドーム33個分に相当する152万平方メートル。
ただの土地開発ではない。「本物の街をゼロから創る」という、狂気にも近い挑戦が始まった。
徹底したリアリズム
- 建材は本国オランダから輸入
- 運河には実際の海水を引き込み浄化
- 電線はすべて地下埋設、一切の“現代感”を排除
- 職人が数ミリ単位で作るレンガの街並み
未来への社会実験
- バイオマスを利用したごみ再資源化
- 海水による地域冷暖房
- 下水処理の自立循環型システム
これは、単なる観光施設ではなかった。環境先進国としての日本の未来像を背負う、国策レベルの実験都市でもあったのだ。
オランダ王室からの許可
シンボルとなる「パレス ハウステンボス」は、現役の王宮であるがゆえ、
オランダ王室から特別な許可を得て再現。
この時点で、ハウステンボスは単なる模倣ではなく、日蘭友好の象徴に昇華していた。
1992年、総事業費2,200億円を投じて、壮大すぎる街は誕生する。
それは「観光」の名を借りた、都市デザイン×環境工学×文化芸術のハイブリッド作品だった。
バブルという時代の偶然と、神近氏という一人の男の情熱が奇跡的に重なったとき、
日本の片隅に、ヨーロッパの“魂”が宿る街が生まれた。
第2部:経営史編──栄光、挫折、そして「1円カレー」が起こした奇跡
■2-1:夢の代償──バブル崩壊と、経営破綻へのカウントダウン
1992年に開業したハウステンボスは、国内初の「本物志向・環境共生型テーマパーク」として華々しいスタートを切った。
しかし、その裏側ではすでに暗雲が立ち込めていた。
経済状況の激変
- 開業と同時期にバブル経済が崩壊
- 想定していた集客数に届かず、施設維持費・返済利息が重くのしかかる
- 入場料・宿泊費ともに高額で、「憧れの街」は次第に「近寄りがたい存在」へ
“本物”の街は、美しさゆえに、更新しにくかった。
一度訪れれば感動する。だが二度目を誘う「変化」がない。
初期投資2,200億円のうち、その大半は街並みの再現と設備に注がれた。
だが、“本物の風景”にはストーリーと再訪理由が必要だった。
そして2003年──経営破綻
創業からわずか11年。
累積赤字が2,000億円を超え、会社更生法を申請。
「夢の街」は、現実に飲み込まれた。
■2-2:救世主・澤田秀雄とH.I.S.が見た“再生の芽”
誰もが匙を投げたハウステンボスに、再建の手を差し伸べたのが、
格安旅行会社H.I.S.創業者・澤田秀雄氏だった。
「ここはまだ終わっていない。街には“可能性”が眠っている。」
経営の大転換ポイント
- 徹底的なコストカットとスリム化
- 不採算部門の見直し、スタッフ数・契約の適正化
- 運営を「観光ビジネス目線」にリシフト
- 顧客満足度優先の価格戦略
- 「1円カレー(期間限定)」「500円ランチ」など、驚きと手頃感の両立
- 高級路線から“楽しく気軽に行ける場所”へとイメージを一新
- イベント偏重から“季節の顔”づくりへ
- 春:チューリップ祭
- 冬:イルミネーション「光の王国」
- 通年で集客できる「テーマ性のある花と光の国」へ
■ 「光の王国」──反対を押し切って輝いた、大逆転の光景
澤田氏が最も反対された施策、それがヨーロッパの街にイルミネーションだった。
社内「歴史的街並みに電飾なんて不謹慎だ」
澤田氏「だからこそギャップが感動を生む」
そして結果は──
年間1,300万球の輝きが、世界最大級の光景を生んだ。
- SNS映えする撮影スポット
- 海外観光客も狙える“幻想的夜景”
- 冬場の集客が激増し、「閑散期」の概念が消滅
■ わずか1年で黒字化
破綻寸前だった街は、1年で経営黒字に転換。
来場者は年間300万人を超え、旅行先ランキングでも常連に返り咲いた。
ハウステンボスの再建とは、単なる経営手腕の物語ではない。
“街”をどう見せるかという、演出と編集の力だった。
第3部:魅力編──知られざるハウステンボスの素顔
■3-1:なぜ“ミッフィー”がいるの?──オランダとの絆の深さ
ハウステンボスを訪れて驚く人も多いのが、園内の随所にあふれる“ミッフィー愛”。
でもそれには、しっかりとした“ルーツ”がある。
- ミッフィー(ナインチェ)は、オランダ生まれの絵本キャラクター
- 作者はオランダの国民的作家、ディック・ブルーナ
オランダ文化を背景に持つハウステンボスと、
ミッフィーの世界観は実は「親和性が最高レベル」なのだ。
2025年6月には「ミッフィー・ワンダースクエア」が誕生し、
2つのアトラクションを擁するミッフィーの国の“新聖地”となっている。
■3-2:「光の王国」はギネス級イルミネーションの殿堂
いまやハウステンボスの代名詞となった「光の王国」。
- 総電球数:1,300万球超
- 点灯面積:65,000㎡以上
- 「光の滝」「運河イルミ」「光と噴水のショー」など独自演出多数
- 国内外のイルミネーションアワードで常に上位入賞&殿堂入り
SNS映えだけではなく、“夜の体験価値”を根本から変えた
「動的演出×静的街並み」の融合事例として、観光学の教材にもなっている。
■3-3:「住めるテーマパーク」という唯一無二の世界観
ハウステンボスは、ただの“遊園地”ではない。
実は、リアルに住める“都市”でもあるのだ。
- 「ワッセナー地区」という高級住宅街を園内に併設
- 実際に分譲住宅が販売されており、住民票も置ける
- 運河沿いにはマイボートを停泊できる私設ポンツーンも完備
日本唯一の「テーマパーク都市」構想は、今なお現役で機能している。
■3-4:アトラクションが今、爆速で増えている理由
近年のハウステンボスは、“静”から“動”への大転換期にある。
その象徴が、1年半で6つの新アトラクションを導入するという、
前代未聞のスピード感だ。
代表的な新アトラクション例
- ミッション・ディープシー(2024春):深海探査型シューティングライド
- ミッフィー・ワンダースクエア(2025年6月):小さな子ども向けライド
- エアクルーズ・ザ・ライド(2025年9月):日本初上陸の大型没入型ライド
- ホライゾンアドベンチャー・リニューアル:旧名作アトラクションの完全復活
新投資のキーワードは、「短期集客×長期価値創出」。
美しい街並みに加え、“体験型”エンタメが本格始動している。
ハウステンボスの魅力は、見た目の美しさだけではない。
“トリビアの宝庫”としても、語り継ぐ価値がある街なのだ。
第4部:未来編──次なる100年へ、ハウステンボスが描く新世界
■4-1:再び動き出した街──PAGによる“第二の開国”
2022年、ハウステンボスは新たなステージへと移行した。
H.I.S.による復活劇ののち、今度は香港の投資ファンド「PAG」が親会社となる。
「日本が持て余していた宝石に、世界が再び注目し始めた」
PAGは明言する──
「アジアを代表するエンタメリゾートへと育て上げる」と。
かつての「オランダの街並み再現」から、いまや
アトラクションの導入スピード、施設開発、コラボ戦略において
“世界基準のテーマパーク”としての戦いが始まっている。
■4-2:「使っていない土地」こそ、未来の宝
ハウステンボスは、実はまだ未開発エリアが多数残されている。
- ホテル・商業施設の新設
- eスポーツ、VR/AR体験施設、教育ツーリズムとの連携
- ゲーム・アニメ企業とのメディアミックス連動
- 九州各地との地域連携型観光モデル
これらの開発は、東京には真似できない広大な敷地と一体性によって可能になる。
街全体を“エンタメ・キャンパス”にするという夢が、
今ようやく「現実路線」で語られ始めた。
■4-3:「美しさ」と「驚き」が共存する都市モデルへ
過去のハウステンボスは、美しいが静的だった。
現在は、驚きに満ちた動的なエンタメを融合し始めている。
未来は、そのさらに先──
“静×動×知”を統合した「都市としての“感動体験”の舞台」になることだ。
- 住まう街
- 学ぶ街
- 働く街
- 遊ぶ街
- 想像する街
それらを一つのコンセプトで包み込むリゾート型未来都市。
かつて神近氏が夢見た「未来のまちづくり」の理想は、
ようやく“テクノロジーと世界視点”を得て、動き出そうとしている。
終章:夢は、まだ終わらない
「ハウステンボス」──Huis Ten Bosch。
それは英語の“House”ではなく、オランダ語で「森の家」を意味する言葉。
自然と共に生きる文化、静けさと洗練、そして希望を宿す場所。
その名が示すとおり、ハウステンボスは最初から“街”であり“理念”だった。
一人の男の夢が、バブルという時代と結びつき、
都市デザインの限界を押し広げ、
美しすぎる街を生んだ。
だがその街は、過去の重みに沈みかけ、
世界から見放され、誰もが諦めかけた時──
また別の夢想家が現れ、奇跡の再生を成し遂げた。
そして今、世界市場とテクノロジーを武器に、
三たび「未来の扉」を叩こうとしている。
ハウステンボスは完成された街ではない。
むしろ常に、未完成であり続ける「生き物」だ。
- 美しさを守りながら変化し、
- 静けさの中に熱狂を宿し、
- 理想と現実の間で揺れながらも前に進み続ける
それは、理想都市の“プロトタイプ”であり、
日本が世界に示せる「都市づくりの物語」でもある。
次にあなたが訪れる時、そこにあるのは、
見たことのある街並みかもしれない。
けれど、まったく新しい“感動”が、あなたを待っている。
この壮大な物語には、まだ続きがある。
なぜなら、夢はまだ、終わっていないからだ。

「ただの観光地じゃなかったんだブー!」
「“街そのものがアトラクション”って…ちょっとロマンあるブーね」




















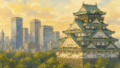

コメント