「トントントン・ツーツーツー・トントントン」──。
映画やドラマでおなじみのこのリズム、誰もが知る世界共通の“助けて”サインだ。
だが意外にも、「SOS」に意味はない──そう聞いて驚く人も多いのではないだろうか。
本記事では、あまり知られていない「SOS」誕生の舞台裏と本当の理由に迫っていく。
【第1章】「SOS=Save Our Ship」はウソだった?
まず多くの人が誤解しているのが、「SOS」の由来。
よく聞く説は──
といった、“頭文字”説。

「ドラマとかアニメでよく見るけど、実は後付けの“こじつけ”なんだブー!」
実際、関東総合通信局も以下のように説明している。
「“SOS”という文字自体に意味はありません。伝達しやすく、間違えにくい信号だから採用されたと考えられています」
つまり、単純・明確・伝達ミスを防ぐためだけに選ばれたもの。
「助けて」の想いは込められているが、単語の略称ではないのだ。
【第2章】モールス信号の“トントントン・ツーツーツー・トントントン”
「SOS」をモールス信号で表すとこうなる。
・・・ーーー・・・
(トントントン・ツーツーツー・トントントン)
・(トン)=短点=素早い信号
―(ツー)=長点=長めの信号
このリズムが簡単で覚えやすく、どんな緊急時でも誰でも素早く打てるのが最大のポイントだ。
映画やドラマでよく耳にする「トントントン・ツーツーツー・トントントン」は、まさにその特徴を象徴するサウンド。
ちなみに、アーティスト「こっちのけんと」の楽曲『はいよろこんで』の中にも、「・・・ーーー・・・」という印象的なリズムが繰り返し登場する。
楽曲では特に“モールス信号”や“SOS”とは明言されていないが、このリズムこそ世界共通の遭難信号そのもの。
曲中には「ギリギリダンス」や「鳴らせ君の3〜6マス」など、苦境の中でも生き抜く力強さやユーモアに溢れているが、その中に“密かに助けを求めるサイン”が忍ばせてあるとすれば──。
気づいた瞬間、楽曲の聴こえ方も変わるかもしれない。

「実は“助けを求めるサイン”が隠れてたって面白いブー!知ってると、より深く楽しめるブー!」
【第3章】「SOS」はいつ世界標準になったのか?
正式に「SOS」が国際的に決まったのは、1908年のこと。
- 1906年:ドイツ提案で「SOS」案が浮上
- 1908年:第2回国際無線電信会議で正式採択
当時、船舶の無線通信技術が発展し、世界中で遭難時の統一信号が求められていた。
「単純明快・覚えやすい・伝えやすい」をすべて満たすとして、「SOS」が選ばれたのだ。
“世界共通の助けて”サインは、実用性最優先で生まれたものだったのである。
【まとめ】意味はなくても「命をつなぐ言葉」
「SOS」は略称ではない。意味もない。
それでも、たった3文字に世界中の人々が即座に反応できる。
そのシンプルさこそ、命を救う鍵だったのだ。
そしてそのリズムは、今も映画・ドラマ・音楽のなかでさりげなく使われ続けている。
次に「トントントン・ツーツーツー・トントントン」が聞こえたときは、その裏に込められた“救助の歴史”を、少しだけ思い出してみてほしい。

「助けを求める声は、シンプルが一番伝わるブー! でも…できれば出番がないのが一番だブー!」





















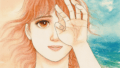
コメント