「友達が溺れた。姿が見えない──」
13歳の中学生が夏の川遊び中に流され、命を落とした。
岐阜県・木曽川で起きたこの痛ましい事故は、夏になると繰り返される“風物詩化された悲劇”のひとつにすぎない。
いったいなぜ、私たちは毎年のように同じ報道を目にしながら、事故を繰り返してしまうのか?
「舐められた自然」「川だから平気」という油断が、若い命を奪っていく構図とは──

「“夏の川遊び”が、“死に至る遊び”になってしまうのは何でだブー…?」
第1章:またも木曽川で──13歳の少年が流された現実
事故は2025年7月26日午後2時40分ごろ、岐阜県可児市・木曽川左岸公園付近で起きた。
「友達が溺れた。姿が見えない」との通報で消防が出動し、約2メートルの水深の川底で13歳の男子中学生が発見された。
搬送されたが、その後死亡が確認された。
現場には友人4人もおり、仲間との川遊び中の悲劇であることがわかっている。
- 流されたのは水深2mの“岸近く”
- 複数人で遊んでいたが、救助が間に合わなかった
- 通報は即座だったが、水中での発見が難航
事故のパターンは典型的だが、それがゆえに、「またか」と思われがちである──
しかしその“慣れ”こそが、問題の本質なのかもしれない。
第2章:「川だから大丈夫」はどこから来るのか?
私たちは、どこかで「海より川の方が安全」と思っている。
理由は簡単だ。
- 流れが見える
- 波がない
- 浅そうに見える
- 入りやすい場所が多い
こうしたイメージが、“自然”ではなく“公園”や“レジャー施設”のように見せてしまうのだ。
川は「危険が可視化されにくい自然」。流れも深さも見た目では判断できない。
第3章:川の“見えない危険”──本当に怖いのは底流と変化
実際、川での水難事故のほとんどは、流れが穏やかに見える場所で起きている。
- 水底の深さが急変する場所
- 見えない“逆流”や渦巻き
- 雨による上流の増水の“時差”
- 滑りやすい石・苔・浮石
- 急な足のつかないゾーンの出現
見た目の穏やかさと、本当の危険が乖離しているのが“川”という場所なのだ。

「“あそこなら浅いし大丈夫”って言葉、何度聞いたかわからないブー…!」
第4章:なぜ報道されても事故は減らないのか?
毎年、同じような事故が報道されている。
SNSでも拡散され、メディアも注意を呼びかける。
それなのに、「自分は大丈夫」という心理が事故を繰り返させる。
これは心理学でいう正常性バイアス(自分だけは平気と思い込む)の典型だ。
また、川遊びは大人が目を離しやすいレジャーでもある。
- 自然に近いけど遊び場っぽい
- 子どもだけで遊ばせやすい
- 危険を察知しにくい
こうした“危険だけど手軽”という川の特性が、事故の温床になっている。
第5章:事故を“防ぐ”から“前提にする”へ
本当の意味で事故を減らすには、
「川は危険である」という前提を徹底させるしかない。
- ライフジャケット着用を“必須化”
- 友人同士だけでの遊泳を避ける
- “足がつかない=立ち入り禁止”の意識
- 事故例の“具体的な共有”と可視化
また、地域ごとに「ここは過去に死亡事故あり」など、“事故情報の地図化”も有効だ。

「“危ないから行くな”より、“ここで何が起きたか”を知ることが大事だブー!」
結論:「夏の川遊び」は、自然との共存リテラシーが問われる
川は、遊び場じゃない。
自然であり、命を奪いうる存在である。
その当たり前が、
レジャーと化した“手軽な自然”の前では簡単に忘れられてしまう。
だからこそ私たちは、
「事故があった」という事実だけでなく、
“なぜ事故が繰り返されているのか”という構造に目を向けるべきだ。
まとめ
- 岐阜県木曽川で13歳の男子中学生が溺死
- 毎年繰り返される川遊び中の死亡事故
- 見た目に反して“川は非常に危険”
- 川への油断と正常性バイアスが事故を助長
- 「予防」より「前提」としての危険認識がカギ
事故が起きたその場所で、去年も誰かが流されていたかもしれない。
そして、来年も──同じ場所で、同じことが繰り返されるかもしれない。
そうならないために、
“舐められた自然”に対して、
もう一度、敬意を取り戻さねばならない。




















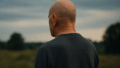

コメント