飛行機に乗ると必ず耳にする「携帯電話は機内モードにしてください」というアナウンス。
けれど──実際に“スマホが原因で飛行機事故が起きた”という事例は、世界で一度も存在しない。
ではなぜ、今もなおこのルールは守られ続けているのか。
科学的根拠から社会的背景、そして心理的効果まで、多角的にひも解いていく。

「事故ゼロなのに残ってる理由、気になるブー!」
第1章 「機内モード」ルールの起源
1990年代後半から2000年代にかけて、携帯電話の普及と航空安全の懸念が重なった。
当時の携帯は電波出力が強く、周波数帯も航空機の通信機器やナビゲーション機器に近かったため、
「干渉して計器が狂うのでは」という恐れが国際的に共有されていた。
実際、アメリカ連邦航空局(FAA)や欧州航空安全局(EASA)には「機器に雑音が入った」との報告が寄せられ、
予防的に 「電源オフ」=安全最優先 のルールが導入された。

「まだガラケー時代、電波もパワフルすぎたブー!」
第2章 本当に事故は起きたのか?
結論から言えば──
携帯の電波が原因で墜落など重大事故に至った事例は、世界で一度も確認されていない。
ただし、パイロットが「通信に雑音が入った」「ヘッドセットから不明なノイズが聞こえた」と証言したケースは複数ある。
たとえば、基地局を探す携帯が一斉に電波を発する離着陸時、
航法システムのモニターに一瞬のノイズが走った、という報告は残っている。
“事故はゼロ、異常の報告はある”──このグレーな実態が、ルールを残した最大の理由だ。

「ゼロだけど、完全に無害とも言い切れないブー!」
第3章 150台同時使用のシナリオ
仮に乗客150人が一斉に機内で携帯を使ったらどうなるか。
- 各携帯は「つながる基地局がない!」と認識
- 電波を最大出力にして基地局探索を繰り返す
- 結果、バッテリーは急速に消耗
- その大出力が機内機器の周波数帯に“かぶる”可能性も
実際の影響は「ほぼゼロ〜微弱」だが、
安全限界ギリギリの離着陸時に“もしもの一瞬”が起これば大惨事につながりかねない。
だから「念のため」ルールは残っている。
第4章 なぜルールは今も“健在”なのか?
現代のスマホは電波規格も進化し、航空機器との干渉リスクはほぼ解消されている。
それでもルールが生き残る理由は4つある。
- 統一のため
国や機材ごとに「使える/使えない」を区別するより「一律禁止」の方がシンプルで徹底しやすい。 - 極限時の安全確保
航空の基本は「ゼロリスク」。離着陸という緊張状態でノイズ要因を排除するのは当然とされる。 - 乗客の行動管理
機内モードは“安全上のお願い”であると同時に、乗客に「離着陸時は集中して行動を控える」ことを促す役割を果たす。 - 電波法や国際条約の名残
航空と通信は両方とも国際管理下にあり、更新には時間がかかる。ルールは保守的になりがちだ。
第5章 世界の潮流と「解禁」の波
実はここ数年、欧州を中心に 「機内5G解禁」 が進んでいる。
EASAは航空機に専用基地局(ピコセル)を設置し、外部との干渉を防ぎながら通話やデータ通信を可能にするシステムを承認済み。
ただしこれは、航空会社が設備を整備した機材に限られる。
大半の便では依然として「機内モードにしてください」が基本だ。

「全便OKじゃないから、やっぱり機内モードは現役ブー!」
第6章 心理的・社会的側面
ルールには科学的合理性だけでなく、心理的な安心感も作用している。
- 「全員が機内モードにしている」という一体感
- 客室乗務員が安全管理をコントロールしているという信頼
- ルールを守ることで「飛行機は安全だ」と思える心理効果
これはいわば、 安全の“儀式” でもある。

「ちょっとおまじない的な側面もあるブー!」
第7章 結論──なぜ残るのか?
- 携帯で事故は起きていない
- だが、ノイズや異常の報告はある
- 航空は「1%の可能性」さえ排除する文化
- さらに心理的安心・行動管理の意味も大きい
したがって機内モードは、科学的根拠+社会的理由+心理的効果が折り重なった “残存ルール” なのだ。

「なるほど、機内モードは“ゼロリスク+安心感”の象徴なんだブー!」





















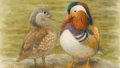
コメント