月曜の朝4時15分。
週の始まりにして、最も静かな時間帯にひっそりと放送されている音楽番組『はやウタ』(NHK総合)。
多くの人が寝ているであろうこの時間帯、しかも「再放送」ではなく、れっきとした“新作”として編成されているのだ。しかも、これが5年近く続いている。
「誰が見るの?」「なぜこの時間?」「なぜ終わらないの?」そんな疑問と共に、月曜朝のテレビ欄に鎮座し続ける『はやウタ』。
今回は、この番組が“なぜこの時間に、今もなお新作で放送されているのか”を、NHKの編成事情・視聴者層・制度的背景などから探ってみたい。
【1】『はやウタ』ってどんな番組?
『はやウタ』は、演歌・歌謡曲・ミュージカルなどを中心に、ベテランから若手まで多彩な歌手が出演する30分の音楽番組。
2021年4月にスタートし、司会はミュージカル俳優の井上芳雄さんとNHKアナウンサーの宮﨑あずささん。ルーツは、午後の番組『ごごナマ』内で放送されていた『ごごウタ』コーナーにある。
『ごごナマ』終了後も“形を変えて継続”されたこの番組は、現在も月曜早朝4:15〜4:45に不定期(概ね隔週)で新作放送が続いている。
【2】なぜ「月曜早朝4時台」なのか?
この疑問は多くの人が抱くところ。
月曜といえば週の始まり。朝4時台といえば、大多数の人がまだ就寝中。しかも会社・学校も数時間後には始まるというタイミングだ。
にもかかわらず、なぜこの時間に“新作”が編成され続けているのか? いくつかの考察が成り立つ。
【3】“高齢視聴者層”という固定ターゲット
NHKのコア視聴者層には早起きの高齢者が多いとされる。演歌や歌謡曲といったジャンルのファン層とも重なるため、早朝4時台という時間帯でも“視聴者ゼロ”ではない。
また、漁業・農業・市場勤務・タクシードライバーなど、早朝に活動を始める層も一部存在する。そうした層に向けた“静かな音楽番組”として成立しているとも考えられる。
【4】編成上の“空き枠”へのフィット
もうひとつの大きな要素は、NHK全体の編成事情にある。
火曜〜金曜の早朝4時台には、前日深夜のBS『国際報道』の再編集版が地上波で放送されている。しかし、日曜夜にはBSで『国際報道』が放送されていないため、月曜早朝のこの枠だけ“ぽっかり”空くのだ。
つまり、週の中で唯一編成が宙ぶらりんになるこの月曜朝4時台に、『はやウタ』が“ピースとして綺麗にはまっている”と見ることもできる。
【5】アーティスト側の“需要”とNHKの“文化的使命”
演歌・歌謡曲のアーティストにとって、テレビ出演は今も重要なプロモーションの場。『はやウタ』は、深夜であっても“新曲披露の場”として機能している。
また、NHKには「多様な文化の紹介」という公共放送としての使命もある。若者向けのJ-POP特集やアニメ特番に偏らず、演歌・歌謡曲といった“伝統文化”を扱い続けることは、ある意味で“NHKらしさ”を体現しているとも言える。
【6】でも…「せめて日曜早朝にすれば?」というツッコミ
もちろん疑問は尽きない。

「月曜じゃなくて、せめて日曜の早朝でよくない?」
「見る人、もっといるんじゃ?」
これはまったくその通りである。だが、前述の通り日曜夜の『国際報道』が存在しない=翌早朝枠が空いているという編成事情、そして“あえて静かな月曜朝に音楽を流す”という“時間帯そのものを演出に使っている”という視点も、ある意味では納得できる部分もある。
【まとめ】
『はやウタ』が月曜早朝4時台に新作で放送され続けているのは、
- 高齢者層など限られた視聴者へのピンポイント対応
- NHK編成における「月曜だけ空く」という特殊な構造
- 文化発信としての役割
- 出演者・音楽業界からの一定のニーズ
これらが重なった結果の“静かな継続”なのだろう。
さらに近年では、NHKプラスやNHKオンデマンドなどネット配信も視野に入れた放送戦略が進んでいる。『はやウタ』のように地上波で形だけでも放送されることで、配信対象番組として扱いやすくなり、ネット上での“キャッチアップ視聴”やアーカイブ価値のある素材として活用しやすくなる側面もある。
あの不思議な放送時間の裏には、
これぞまさに、テレビ編成の“OFF”な話題。次に4時15分に目が覚めた時、ふとテレビをつけてみてはいかがだろうか。




















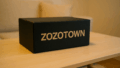

コメント