北海道で40℃──。
これまで「避暑地」とされてきた北の大地が、いま観測史上初の猛暑に見舞われている。
だが、問題は気温そのものではない。「クーラーがない」家庭が6割という現実が、命を危険にさらしているのだ。
断熱性の高い住宅、短い夏、夜の冷え込み──あらゆる生活文化が「冷房不要」の前提で築かれてきた北海道。
だが、気候の変化はその“前提”を根底から覆しつつある。
避暑地神話の終焉。
そして「冷房は贅沢ではなくライフライン」になる日。
今、北海道の暮らしが試されている。
第1章:40℃に迫る北海道、想定外が“現実”になる
「北海道で40℃」
かつてなら冗談のように聞こえたこの予報が、いま、現実として目の前にある。
7月22日、北見市では38℃を観測。24日には帯広市で40℃、北見市で38℃、札幌市と旭川市、岩見沢市では36℃くらいと予測され、フェーン現象と大陸からの熱波が重なって、かつてない猛暑に見舞われている。
全国では今年2回目の「猛暑ピーク」。すでに200地点を超える猛暑日(35℃以上)が観測され、30都道府県に熱中症警戒アラートが出された。
しかし、本州と違って北海道には決定的な“弱点”がある。
──それは「冷房が前提でない」生活インフラだ。
第2章:冷房なしの現実──保有率42%、過半数が持たない
2021年にウェザーニュースが行ったアンケートによれば、北海道のクーラー保有率はわずか42%。
つまり6割近い家庭が冷房を持っていない。
これまではそれで問題なかった。
夏でも25℃前後のカラッとした気候。夜には長袖が必要な涼しさ。
「北海道の夏は過ごしやすい」と言われ続けてきたが、それはもう過去の話になろうとしている。
気温は上がっても、“冷やす手段がない”──それが最大のリスクだ。
- 冬の寒さ対策として高断熱住宅は多い
- 夏の冷房設備は設計から除外されがち
- エアコン設置スペースが物理的に無い家も多い
第3章:L字放送と“クーリングシェルター”の重要性
この暑さの中、北海道のテレビでは、L字画面で熱中症警戒と避難先の情報を放送している。
特に注目されるのが、「クーリングシェルター」と呼ばれる冷房付きの公共施設の紹介だ。
- イオンなどの大型商業施設
- 図書館、公民館
- 道の駅や温泉施設のロビー
こうした場所は「誰でも入れる・冷房が効いている」ことが重要で、家に冷房がない人の命綱となる。

「テレビが“涼しい避難先”を教えてくれるなんて、昔は考えもしなかったブー…。
熱中症は気合じゃ防げないブー!」
東京や大阪ではあまり見られないこのスタイルだが、災害レベルの暑さに対して行政とメディアが役割を果たす新しい形が、北海道で芽吹いている。
第4章:熱中症の“前兆”を見逃すな
熱中症は、ある日突然倒れるものではない。
じわじわと脱水が進み、のどの渇きや足のつり、頭痛・めまいといった前兆が現れる。
しかし、涼しい場所に避難する判断が遅れると、取り返しがつかない。
- のどが渇く
- ふくらはぎがつる
- めまいや頭痛
- 意識がぼんやりする
→すぐに冷房の効いた場所へ移動し、経口補水を!
特に高齢者や小さな子どもは、自覚症状が出づらく、周囲が気づいたときには重症化しているケースも多い。
第5章:北海道の家づくりに“冷房”を組み込む時代か
ここから先、北海道で住宅を建てるとき、
“断熱”と並んで“冷房”が求められる時代が来るかもしれない。
- エアコンを設置する間取り設計
- 電力インフラの見直し(ピーク負荷)
- 高齢者施設や学校の空調整備
- クーリングシェルターの平常時からの周知
それは単なる「快適性の向上」ではなく、命を守る社会基盤づくりだ。
まとめ:涼しさは“贅沢”から“ライフライン”へ
かつて、「クーラーがなくても暮らせる土地」として羨望された北海道。
だが、いまやその特徴が逆に命を脅かす“構造的リスク”へと変わってきている。
異常気象はもはや“異常”ではない。
そして、冷房はもはや“ぜいたく”ではない。
冷房は、命を守る装置。
その前提に立った街づくり・暮らしづくりが今、6割近い家庭で冷房のない北海道で試されている。

「“自然の涼しさ”に頼れないなら、“文明の冷たさ”に守ってもらうしかないブー!」



















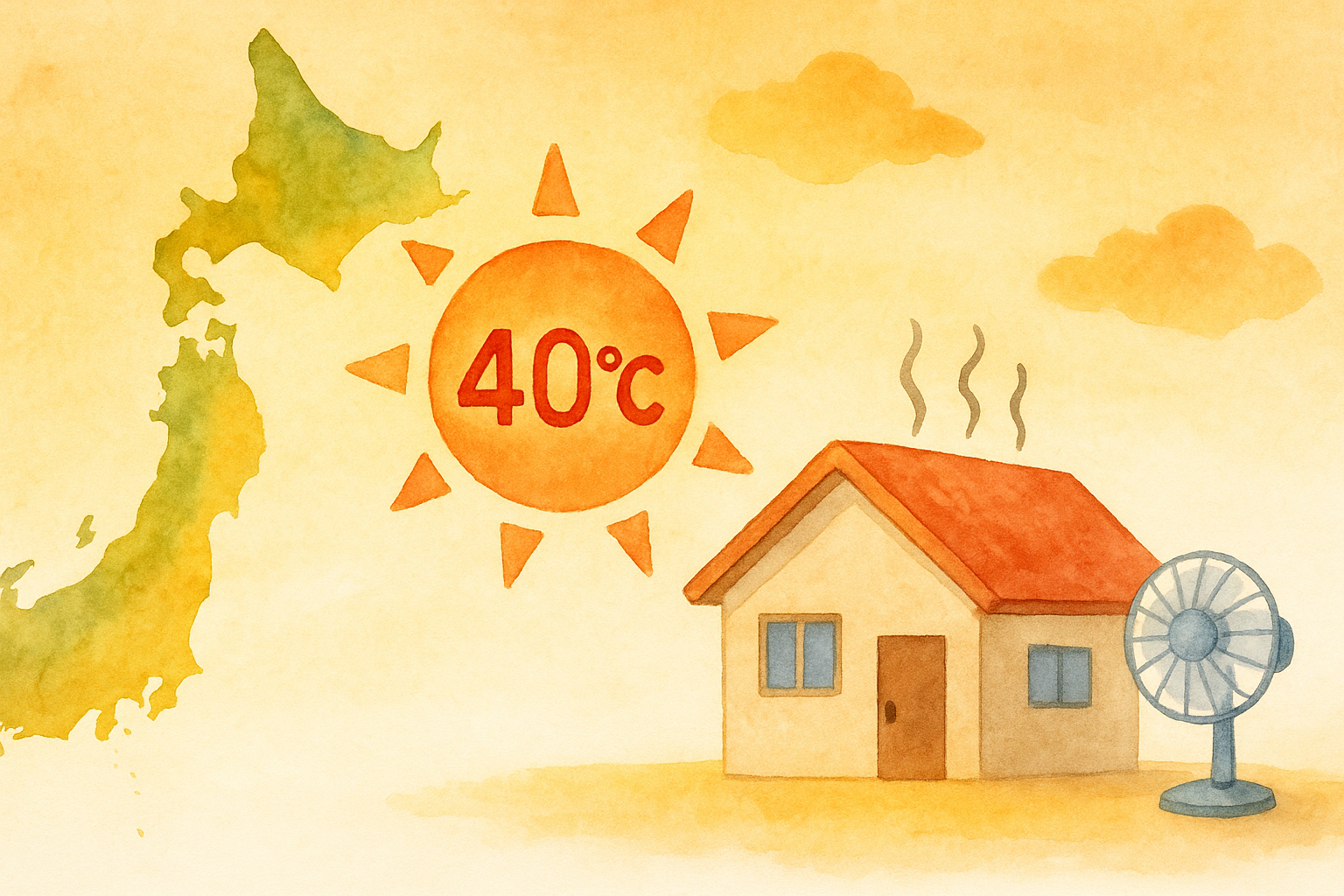


コメント