「タトゥーを入れただけで、どうして“炎上”するのか?」
ファッション、アイデンティティ、自己表現──。それぞれの理由で肌に刻まれたインクに対し、なぜここまで激しい拒否反応が起きるのか。
今、話題の中心にいるのはシンガーソングライターのあいみょん。
女性誌の表紙に映り込んだワンポイントのタトゥーが、SNSで“まさかの炎上”を招いた。さらに、元欅坂46の長濱ねる、嵐の大野智など、「タトゥーと距離があるはず」と思われていた人物たちに次々と視線が集まっている。
好感度、イメージ、公共性…。
日本社会に残る“見えないルール”と、芸能人の自由とのあいだにあるギャップと余白を見つめなおしてみたい──。
■ 「タトゥー=反社」じゃない。でも「好感度」は揺らぐ?
2025年の日本。
タトゥーは「ファッション」として市民権を得たはずだった──。
…にもかかわらず、あいみょんのタトゥーが写り込んだだけでSNSは騒然となった。
『GINZA』9月号の表紙。左腕に映るタトゥーがきっかけで、
- 「そういう人なんですねって目で見られる」
- 「ショックすぎる、嫌いになりそう」
- 「タトゥー、シールであってくれ…」
といった“拒絶の声”があがったのだ。
確かに、タトゥーを入れている芸能人は少なくない。
浜崎あゆみ、土屋アンナ、優里、YOASOBIのAyase…。
でも“あいみょん”が、という点に衝撃が走った。
■ なぜ、あいみょんが叩かれるのか?
その違和感の正体は、“キャラとのギャップ”だ。
- 等身大の恋を歌うフォーク的世界観
- キリン「淡麗グリーンラベル」の爽やかCM
- 『ブラタモリ』のナレーション担当という「公共イメージ」
これらが積み重なっていたぶん、“素朴で親しみやすい人”という印象が強すぎたのだ。
だからこそ、ほんの小さなタトゥーで「裏切られた」と感じてしまう人がいる。
■ 「悲しいよ」──同じ反応が向けられた、長濱ねるにも
元欅坂46の長濱ねるが写真集で“左脇のハート”タトゥーを見せた際にも炎上。
- 「清純派だったのに…」
- 「クリーンなイメージが…」
- 「シールであってほしい」
“元・清純派”というラベルが、皮肉にも本人の選択を制限する“足かせ”になっているのかもしれない。
写真集側もあえてアップ写真を掲載し、意図的に見せている様子。
もはや「見せるタトゥー」はポーズなのか、それとも覚悟なのか──。
■ さらに燃えた「国民的アイドル」のタトゥー
嵐の大野智(44)もタトゥーが報じられたのは記憶に新しい。
- ラフな格好
- ワイルドなヒゲ
- “蓮”のようなデザインが入ったタトゥー
「推してた自分がバカみたい」
「復帰する気がないように見える」
ファンの“想像していた大野像”との落差に、多くがショックを受けた。
■ NHKに“出禁説”まで?──番組への影響論
一部では、タトゥーがNHKの出演に影響するとの声も。
- Ayase(YOASOBI):紅白落選の理由に疑惑
- ディーン・フジオカ:番組内でタトゥーをテープで隠す演出
- 優里:地上波出演が減少傾向?
- あいみょん:「ブラタモリ」ナレーション継続はどうなる?
とはいえ、表に出ない規定や“忖度”が関係している可能性は高く、明確な基準がないまま判断されているのが実情だ。

「ファッションの自由があっても、“好感度”は自由じゃないブー…。
見る側のイメージって、けっこう強烈なんだブー…!」
■ なぜ日本では「タトゥー=拒絶」なのか?
あいみょん、長濱ねる、大野智──彼らに注がれる視線の背景には、「なぜ日本ではここまでタトゥーが嫌われるのか?」という根深い問いが横たわっている。
それは決して“好み”や“世代間ギャップ”だけでは語れない、日本独自の文化的文脈がある。
◆ 江戸の罪人、背中に刻まれた記号
日本では「タトゥー」は“アート”ではなく、“処罰”として始まった。
江戸時代、入墨刑と呼ばれる刑罰が存在し、罪を犯した者に顔や腕に入れ墨を施し、社会からの可視的な排除・烙印として使われていた。
その記憶は時代が下っても消えず、明治期になると「刺青=未開の象徴」として西洋化の流れの中で全面的に禁止。
これにより、刺青は地下へと潜り、やがて“任侠の象徴”として再浮上する──。
◆ 「背中の龍」が意味したもの
昭和のヤクザ映画や漫画では、刺青=アウトローという演出が繰り返された。
この図像的な刷り込みにより、「刺青を見ると怖い」「刺青をしている人は近寄ってはいけない」という感覚が、文化的な反射神経として日本社会に根づいていく。
プール、温泉、ジム──公共空間での「タトゥーNG」ルールがいまなお根強いのも、この“負のイメージ”が制度にまで組み込まれている証だ。
◆ 世界では“アート”、日本では“スティグマ”
一方で、欧米やアジアの一部では、タトゥーは自己表現やカルチャーの一部として広く認められている。
軍人が仲間との絆を記録し、ミュージシャンが信念を刻み、モデルや俳優が美意識として身につける。
“タトゥー=個人の物語”という価値観が共有されている。
対して日本は、公共性・同調性・清潔感を重んじる文化。
個人の美意識よりも、「周囲がどう思うか?」が優先されがちだ。
「見た目が怖い」「印象が悪い」
そんな拒否反応の奥には、“よく知らないものへの不安”があるのかもしれない。
タトゥーを一概に否定することは、その人の背景や選択をまるごと否定することにもつながる。
そこに“反社会性”があるかどうかは、デザインではなく、行動が語るはずだ。
■ タトゥーを受け入れる社会に必要なのは「共存の余白」
“自由にタトゥーを入れる権利”は、誰にでもある。
でもその自由には、他人の視線や偏見という「代償」もついてくる。
- 「見た目で判断しないで」と願う気持ち
- 「こういう人だと思ってたのに…」と嘆く気持ち
その両方が、決して“間違い”ではない。
だからこそ大事なのは、「自分と違う価値観を認める余白」かもしれない。
■ 最後に:タトゥーは“罪”じゃない。でも“ズレ”は残る
時代は変わった。
けれど、すべての人の価値観が同じスピードで変わるわけじゃない。
あいみょんの左腕、長濱ねるのハート、大野智の上腕。
それは、ただのインクの絵ではなく、社会の“反応”を映す鏡になっているのかもしれない。

「タトゥーにびっくりするのはわかるブー。でも、そのインクの下には、誰かの想いとか、選んだ人生とか、ちゃんとあるはずだブー。
見た目じゃなくて、まずは“中身”に目を向ける社会であってほしいブーね」




















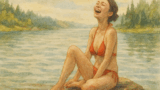


コメント