最近のバラエティ番組やトーク番組を見ていると、
場面再現や補足説明のシーンに、こんなテロップが出ることが増えている。
「※この画像はAI生成です」
かつては“いらすとや”が万能素材として使われていたテレビのイメージ画像が、
いまや生成AIツールによる作画に、静かに置き換わりつつある。
その背景には、制作現場のスピード要求・コスト圧縮・汎用素材化があり──
そして、これまで業界を支えてきたイラストレーターたちの仕事は、確実に影響を受け始めている。
■ テレビの“イメージ画像”に起きた変化
◆ いらすとや時代(〜2020年代前半)
- 無料・著作権OK・シンプルで伝わりやすい
→ 汎用イメージ素材としてテレビやWebメディアで爆発的に普及 - 「描き下ろしは予算と時間がかかる」という理由で
“とりあえずいらすとやで補完”が常態化 - 結果:指名されないイラストの仕事が激減
◆ 生成AIの登場(2023年〜)
- スタッフ自身が無料/格安ツールで“そこそこ見栄えのする絵”を即生成
- 特に1シーンあたりのカット数が多いバラエティでは
「スピード>品質」傾向が顕著に - 「いらすとや」さえ使わず、外注もスルーというケースが急増

ブクブー
「気づいたら、「描いてもらう」が「つくる」になってるブー。
AIは“発注を飛び越えて”きたんだブー…」
■ なぜテレビはAIや無料素材を選ぶのか?
| 要素 | メリット |
|---|---|
| コスト | 外注せずに済む=予算カット可能 |
| スピード | スタッフが即生成→即使用 |
| 修正対応 | テキスト指示だけで出し直せる |
| 権利面の安心感 | 著作権・肖像権のリスク回避(※完全にゼロではないが) |
つまり、現場の効率化ニーズに、AIは完璧にフィットしてしまっているのだ。
■ では、イラストレーターの仕事は“なくなる”のか?
減少傾向が顕著な領域
- 「誰が描いたかは問わない」汎用カット・挿絵・説明図
- 「伝わればOK」のプレゼン資料・Webニュース・テレビの補完素材
こうした仕事は、“代替可能性が高い”ゆえに
AIや無料素材にシフトしやすいポジションにあった
それでも“人の絵”が求められる領域
- 絵本・ゲーム・広告など、ビジュアルそのものが世界観の一部である仕事
- ファンアート・SNS拡散のような、「この人が描いた」という熱量が伝わる絵
- キャラクターデザインやブランド資産との結びつき
つまり──
「誰が描いたか」よりも「その絵の意味」が重視される仕事は、依然として人の領域に残っている。
■ 現役イラストレーターたちの“対応力”
変化の波にどう対応するか?
多くのクリエイターたちは、“ただ描く”から“どう描くか”へと進化を始めている。
◆ 主な動き
- AIに真似できない絵柄・構図・世界観を磨く
- ディレクション・監修・ライセンス管理など上流工程へのシフト
- AIツールを道具として使いこなす側に回る(生成後の加工や着彩など)
- コミッションサイトやSNSを通じて、個人のファンコミュニティを形成

ブクブー
「AIは“絵”を生むけど、“気配”はまだ描けないブー。
ゆらぎ、迷い、感情、憧れ──
そういうものが宿るのは、やっぱり人の手じゃないと難しいブー!」
■ まとめ:変わったのは「発注」じゃなく「発想」
- テレビ業界は「いらすとや→AI」へと移行し、“即時・無料”の素材化が進行中
- その結果、無個性でOKな絵の仕事は確実に減っている
- しかし逆に、「この人にしか描けない」絵の価値は上昇傾向
これからの時代、
イラストレーターは「絵を描く人」ではなく──
“表現を設計する人”
“世界観を構築する人”
として、生き残りの道を切り拓いていくのかもしれない。




















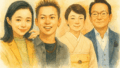
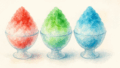
コメント