私たちの食卓に当たり前のように並ぶトマト。サラダに、パスタソースに、カレーに──。
だが、この赤い果実(?)をめぐって、かつてアメリカでは最高裁判所まで争われた裁判があったことをご存じだろうか。
「トマトは果物か、それとも野菜か」。
一見すると子どものクイズのような問いが、国家の税制を揺るがし、裁判官たちを悩ませたのである。
では、最高裁はどんな答えを出したのか──?

「トマトひとつでアメリカ司法が大騒ぎって、すでにオモシロすぎるブー!」
◆ なぜトマトで裁判に?
トマトを前に「野菜か果物か」という議論は、実は単なる雑学ネタにとどまらない。
1893年のアメリカ最高裁判所にまで持ち込まれた、れっきとした司法事件だったのだ。
背景には「お金」がある。
当時、アメリカでは輸入品のうち 果物は関税ゼロ、野菜は関税アリ。
輸入業者は当然「トマトは果物だ」と主張した。関税を免れたいからである。
一方で政府(農商務省)は「トマトは野菜」として課税を迫る。
この小さな食卓の分類問題は、やがて国家的な大論争に発展することとなった。
◆ 科学では果物、生活感では野菜
植物学的に言えば、トマトは種子を含む果実である。
リンゴや桃と同じく、花の子房からできる「果物」の仲間に分類されるのが正解。
だが最高裁は、学問的定義よりも「生活の実感」を優先した。
判事はこう述べている。
「トマトはデザートとしてではなく、メインコースとともに供される。よって野菜である。」
つまり「ケーキに添えるか、スープやサラダに入れるか」で線引きをしたのである。
結果、法律上・商取引上は野菜という判決が下った。
◆ トマト判決が残した教訓
この事件は単なるトリビアではない。
「言葉の定義」と「社会的な実用」がぶつかり合うとき、どちらを優先するのかという普遍的な問いを突きつけている。
- 科学的定義:トマトは果物。
- 生活的感覚:トマトは野菜。
- 法的判断:野菜扱い。
この三層構造が示すのは、「事実」と「制度」と「感覚」の間に常にズレがあるということだ。
◆ 似たような“分類の罠”たち
- ピーナッツはナッツではなくマメ科。
- イチゴは「果実的野菜」と呼ばれる。
- キュウリやカボチャも植物学的には果実。
私たちが日常的に呼んでいる「野菜」「果物」というラベルは、じつは社会的な約束事にすぎないのだ。

「デザートにトマトゼリーを出されたら“果物”かも…?でもカレーに入ったら“野菜”だブー!結局お皿次第なんだブー!」
◆ まとめ
- トマト論争は1893年、アメリカ最高裁にまで発展。
- 植物学的には果物だが、判決は「生活上は野菜」と定義。
- その判断は今も続き、関税や商習慣に影響を与えた。
- この事件は「言葉と制度のズレ」を教えてくれる象徴的な一件。
つまり「トマトは野菜か果物か?」という問いは、
単なるクイズを超えた社会の鏡でもあるのだ。





















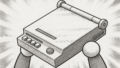
コメント