1995年の発売以来、独特の「カリッ、サクッ」とした食感と豊富なフレーバーで、世代を問わず愛されてきたカルビーのスナック菓子「じゃがりこ」。
コンビニやスーパーで手軽に手に入る“おやつの定番”ですが、その裏側には驚きのエピソードや知られざる工夫がぎっしり詰まっています。
「名前はどう決まったの?」「パッケージのキリンって誰?」
──そんな素朴な疑問に答える形で、商品誕生の舞台裏からSNS時代のアレンジレシピまで、10のトリビアを掘り下げます。
きっと読み終えたら、次に手に取る「じゃがりこ」が少し違って見えるはずです。

「お菓子にここまで物語があるなんてワクワクだブー!」
第1章:「じゃがりこ」の名前の由来は“りかこさん”だった!
「じゃがりこ」──今や誰もが知るスナックの代名詞のような響きですが、この名前が生まれた瞬間にはちょっとした“ひらめき”と“人とのつながり”がありました。
「じゃがりこ」というユニークな名前は、ずばり開発担当者の友人である “りかこさん” に由来しています。
試作品を食べたりかこさんの姿が印象的だったことから、「じゃがいも+りこ(りかこ)」 で「じゃがりこ」と名付けられたのです。
“じゃがいも”と“りかこ”を掛け合わせて生まれたこの言葉遊びが、まさか数十年後まで続くロングセラー商品名になるとは、当時誰も想像していなかったはず。
しかも初期のテスト販売では「じゃがスティック」という、より説明的な名前で売られていたというのも興味深いポイントです。シンプルで分かりやすいけれど、ちょっと味気ない。そこに“りかこさん”の偶然が加わることで、愛嬌ある「じゃがりこ」が誕生したわけですね。
- 名前の由来は開発者の友人・りかこさん
- 「じゃが+りこ」の偶然のひらめき
- 一時は「じゃがスティック」として売られていた

「人の名前が商品名に残るなんて、めっちゃロマンだブー!」
第2章:パッケージのキリンは“ダジャレ”から生まれた!
じゃがりこのカップを手に取った時にまず目に入るのは、あのゆる〜い顔をした「キリン」のキャラクター。
「なぜポテト菓子なのにキリン?」と不思議に思ったことはありませんか?
実はこれ、カルビーらしい“ダジャレ発想”から生まれたアイデア。
「食べだしたらキリ(キリン)がない」──そう、無限に手が伸びてしまうお菓子の魔力を表現したフレーズを、そのままキャラクターに落とし込んだのです。
前例を思い出すなら、「かっぱえびせん」のキャッチコピー「やめられない、とまらない」。
それと同じく、“一度ハマったら止まらない”商品に育ってほしいという願いが込められていました。
単なる動物イラストではなく、「食べ続けちゃう心理」をキリンという存在に重ね合わせるあたり、カルビーの遊び心とマーケティングセンスが光りますね。
- キリン=「キリがない」のダジャレから誕生
- 「かっぱえびせん」のキャッチコピー発想と同じ系譜
- 無限ループで食べ続けてしまう楽しさを象徴

「ダジャレで全国区になるキャラって、すごすぎるブー!」
第3章:キリンには味ごとに“名前と家族設定”がある!
じゃがりこのパッケージをよく見ると、味によってキリンの姿や表情が少しずつ違うのに気づいたことはありませんか?
実はそこには“緻密な設定”が隠されているのです。
カルビーは単に「キリン」というキャラクターを描いただけではありません。なんと、フレーバーごとに名前と家族関係を与えていたのです。
- サラダ味 → じゃがお(お父さん)
- チーズ味 → りかこ(お母さん)
- じゃがバター味 → じゃが作(おじいちゃん)
- たらこバター味 → たら子(親戚キャラ!?)
こうした“キャラ付け”のおかげで、パッケージを見比べるだけでもちょっとした物語性が感じられる仕組みになっているんですね。しかも名前の中に、商品名誕生のキーパーソン「りかこ」が再び登場しているのも遊び心たっぷり。
まるでアニメのキャラクター設定のように、お菓子に「ファミリーヒストリー」を与える発想──これもじゃがりこが子どもから大人まで愛され続ける理由のひとつなのかもしれません。
- 味ごとにキャラの“役割”がある
- ネーミングに再登場する「りかこ」が象徴的
- 単なるパッケージ以上に“世界観”を作り込んでいる

「サラダ味は“お父さん”だったのか!ますます家族感あるブー!」
第4章:10月23日は“じゃがりこの日”だった!
「じゃがりこ」にも記念日がある──そう聞くと、ちょっと驚きませんか?
実は1995年10月23日の発売を記念して、この日が正式に「じゃがりこの日」として制定されているんです。
カルビーはこの日を「ファンへの感謝を伝える日」と位置づけ、これまでにイベントやキャンペーンを開催してきました。SNSでは毎年この時期になると「今日はじゃがりこの日!」と投稿が盛り上がり、自然発生的にお祭りのような空気が広がることも。
単なるスナックの記念日ではなく、「愛され続けている証」として消費者の心に刻まれているのが面白いところです。
なにげなく食べていた“日常のおやつ”が、特別な日を持つ存在になる──これもまた、じゃがりこが文化的なポジションを獲得している証拠といえるでしょう。
- 発売日10月23日=「じゃがりこの日」
- 毎年SNSやイベントで盛り上がる
- スナック菓子を超えて“記念日文化”に根付いている

「自分の誕生日より“じゃがりこの日”の方が覚えてる人もいそうだブー!」
第5章:開発コンセプトは「女子高生がカバンで持ち歩けるお菓子」
1990年代初頭のスナック菓子といえば、袋入りが主流。家でテレビを見ながら食べるスタイルが定番でした。
そんな時代に登場した「じゃがりこ」は、まさに逆張りの発想から生まれます。
当時、流行の最先端を走っていたのは“女子高生”。ファッション、音楽、グルメ、すべてのカルチャーの震源地にいた彼女たちをターゲットに設定し、
「カバンに入れて持ち歩ける」「手が汚れにくい」 という条件を満たすスナックが求められたのです。
その結果生まれたのが、今ではおなじみのカップ型容器。コンビニで買って、そのまま教室や公園でパクッと食べられる──この“モバイル性”が当時としては画期的でした。
言ってみれば、じゃがりこは「ポータブルおやつ」の先駆け。食文化のシーンを“屋内から屋外へ”と拡張させた存在でもあったわけです。
さらに裏話として、カルビーがF1のスポンサーを務めていた時期、
「車のカップホルダーにちょうど収まるように」という発想もケース形状に影響を与えたとされています。
女子高生のカバンだけでなく、ドライバーのドリンクホルダーにもピタッと収まる。
“どこでもスッと取り出せる” という利便性が、あの丸いカップデザインを後押ししたとも言われています。

「F1マシンとじゃがりこカップ…スピード感がすごい取り合わせだブー!」
こうした複数の生活シーンを想定した設計こそ、じゃがりこが“持ち歩き文化”を先取りできた秘密なのかもしれません。
- ターゲットは流行発信源の女子高生
- カバンで持ち歩けるようカップ容器を採用
- 車のカップホルダーにもピッタリ
- 手軽さ&清潔感で「外で食べるおやつ文化」を先取り

「学校帰りにコンビニで買って、そのままベンチで食べるの…めっちゃ青春だブー!」
第6章:独特の「カリッ、サクッ」は偶然じゃなかった!
「はじめカリッと、あとからサクサク」──じゃがりこの代名詞ともいえる食感。
実はこれ、単なる偶然ではなく、開発チームの執念が生んだ成果でした。
当時、カルビー社内には「固いスナックは売れない」という常識があったそうです。
スナックは軽くてふわっとした食感が好まれる、という固定観念を打ち破ったのが若手チームの挑戦でした。
生のじゃがいもを一度“ふかして”から揚げるという、当時としては珍しい製法を試行錯誤。何度も試作品を作り直し、油の温度や生地の厚みを細かく調整し続けた結果、あの「外はカリッ、中はサクッ」のバランスが生まれたのです。
つまり、じゃがりこの食感は「奇跡の産物」ではなく、「逆境を突破した革新の証」。
この成功によって「固めの食感=アリ」という新たな市場価値が生まれ、その後のスナック業界にも大きな影響を与えました。
- 「固いスナックは売れない」という社内常識を覆した
- “ふかしてから揚げる”独自製法で実現
- 偶然ではなく、試行錯誤の末にたどり着いた革命的食感

「噛んだ瞬間のあの“カリッ”は、若手の根性の味だったブー!」
第7章:バーコードにも遊び心!「デザインバーコード®」
パッケージをじっくり眺めたことがある人なら、ふと気づくかもしれません。
じゃがりこのカップの隅にあるバーコード──ただの縞模様ではなく、実は小さなイラストに溶け込んでいるのです。
これは「デザインバーコード®」と呼ばれる仕掛けで、2005年の発売10周年を記念して導入されました。
たとえばチーズ味ならチーズのかけらが乗っかっていたり、サラダ味なら野菜モチーフがあしらわれていたり。
味ごとの個性や遊び心を、わずかなスペースで表現しているんですね。
これまでに登場したデザインはなんと約200種類。
毎回ちょっとした工夫が凝らされていて、知ってしまうと「新しいフレーバーを買うたびにバーコードを確認する」という新しい楽しみ方も生まれます。
お菓子は味が命──でも、じゃがりこは“パッケージの隅っこ”にまで楽しさを忍ばせていたのです。
- 2005年から導入された「デザインバーコード®」
- 味ごとに異なるイラストが隠されている
- これまで約200種類が登場

「バーコードってレジ用だと思ってたけど…アートにもなるんだブー!」
第8章:キャラクターのキリンが登場したのは発売3年後だった!
今では「じゃがりこ=キリン」と言っても過言ではないくらい定着しているあのキャラクター。
でも実は、1995年の発売当初にはパッケージに描かれていなかったんです。
キリンが初めて登場したのは、発売から3年後の 1998年。
「もっと親しみやすさを持たせたい」「お菓子に物語性を与えたい」という狙いから導入されたと言われています。
そこから一気に“じゃがりこの顔”として人気が定着。
単なるお菓子ではなく、「キリン一家の物語を持つスナック」という付加価値を与えたことで、長寿ブランドへと成長していったのです。
考えてみれば、商品って発売当初の姿が“完成形”ではなく、後からキャラクターや世界観を足して進化することも多い。
じゃがりこのキリンはまさにその好例で、ブランドに魂を吹き込む存在になったわけです。
- キリンは発売時には存在しなかった
- 1998年に追加され、定番キャラへ定着
- ブランドに「物語性」を与えることで長寿化に成功

「3年遅れで登場して主役を奪っちゃう…逆転劇だブー!」
第9章:幻の商品名「カリットポテト」
「じゃがりこ」というユニークな名前、今となっては当たり前のように馴染んでいますが──実は世に出る前、他にも候補がいくつか存在していました。
その中のひとつが「カリットポテト」。名前だけ聞けば確かにカリッとした食感を想像できるし、ストレートで分かりやすい。でもどこか“普通”で、今のような愛嬌や親しみやすさには欠けていたかもしれません。
さらに「ポテッキー」「スリムポテト」といった案もあったそうで、もしこちらが採用されていたら、私たちの会話に「今日のおやつはポテッキー!」なんて言葉が飛び交っていた可能性も…。
「じゃがりこ」という響きには、“食感”だけでなく“人の名前”という偶然のエピソードが織り込まれていたからこそ、ブランドとしての厚みが生まれたのでしょう。ネーミングの妙が、ここでも光っています。
- 候補名は「カリットポテト」「ポテッキー」「スリムポテト」など
- 分かりやすいが個性には欠けていた可能性
- 「じゃがりこ」だからこそブランドに愛嬌が宿った

「“カリットポテト”だと…なんかスーパーの安売り感あるブー!」
第10章:SNSで大バズり!アレンジレシピ「じゃがアリゴ」
「じゃがりこ」を単なるスナックとして食べるだけじゃもったいない──そんな発想から生まれたのが、あの伝説的アレンジレシピ「じゃがアリゴ」です。

作り方はシンプル。
カップにお湯を注ぎ、ほぐした「さけるチーズ」を加えて混ぜるだけ。
フランスの郷土料理「アリゴ」を手軽に再現できるということで、SNSで瞬く間に広まり、大きなバズを巻き起こしました。
“固形のお菓子を温かい料理に変える”というギャップの面白さと、チーズがとろ〜っと伸びるビジュアル映え。
それが「#じゃがアリゴ」として数多の写真・動画を生み出し、若い世代を中心に熱狂的なブームを作ったのです。
このレシピは、じゃがりこに新しい命を吹き込みました。
単なる「完成品」ではなく、「自分でアレンジして楽しむ」余地を持つスナックとしての可能性を示したわけです。
※「じゃがアリゴ」はSNSで流行った“アレンジレシピ”ですが、「じゃがりこのカップそのまま」 で作るのは、安全面から見て注意が必要です。
■ カップの材質とリスク
- じゃがりこのカップは 紙製+内側に薄いフィルムコーティング。
- 本来は「常温でスナックを保存・食べる」ことを想定しており、耐熱容器として設計されていない。
- 熱湯を直接注いだ場合、
- 紙の繊維がふやけて強度が落ちる
- フィルムが変形・劣化する可能性がある
- 長時間の加熱や電子レンジ使用は特に危険
■ 想定される危険
- 耐久性低下 → 底抜け・側面がふやけて破損するリスク
- やけど → 崩れたカップから熱湯やチーズが漏れると大惨事
- 衛生面 → コーティング樹脂が高温で劣化する可能性
■ より安全な作り方
- 耐熱容器(マグカップや耐熱ボウル)に中身を移してから作る
- 電子レンジを使うなら 耐熱ガラスや陶器を推奨
- カップは「見た目の演出」用に、できあがったじゃがアリゴを盛り直す程度に留めると安心

「SNS映えは大事だけど、やけどしたら元も子もないブー!ちゃんと耐熱容器を使うのが吉だブー!」
- 「じゃがりこ+お湯+さけるチーズ」で完成
- SNSで“映える料理”として拡散
- スナックを“再構築できる食材”へと進化させた

「チーズがビヨ〜ンと伸びる瞬間、みんな写真撮っちゃうブー!」
まとめ:じゃがりこに隠された“遊び心”と“物語”
1995年に登場してから30年近く──「じゃがりこ」はただのスナックにとどまらず、時代ごとに進化しながら人々を楽しませてきました。
- ネーミングに偶然の“りかこさん”がいたこと
- パッケージのキリンが家族を形成していたこと
- 記念日やデザインバーコードにまで遊び心が詰まっていたこと
- そしてSNS時代には「じゃがアリゴ」という新たな食べ方が誕生したこと
ひとつひとつの要素は小さな工夫やアイデアですが、それらが積み重なって「愛され続ける理由」になっています。
お菓子は口に入れて消えてしまう“儚いもの”ですが、じゃがりこには“消えない物語”が宿っているのかもしれません。
次に手に取るときは、カリッと噛むその瞬間に、開発者たちの思いやユーモアに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

「ただのお菓子じゃなくて、“文化”になってるのがすごいブー!」




















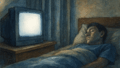
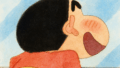
コメント