「酒と泪と男と女」。
そのフレーズだけで、“豪快に酒をあおる昭和の男”を思い浮かべる人も多いだろう。
シンガーソングライター・河島英五は、まさにその象徴だった。
だが──彼は本当に「酒の飲みすぎ」で早世したのだろうか?
2001年、48歳という若さで亡くなった彼の死因は、C型肝炎を原因とする肝硬変。
じつは、彼自身が最もその“酒のイメージ”に悩み、距離を置き、
長年にわたって病と静かに闘っていたという事実は、あまり知られていない。
亡くなる2日前までステージに立ち、
“酒を断ちながら、酒の歌を歌い続けた男”の最期とは──。
今回は、河島英五という人物を、「酔いどれ伝説」ではなく、「歌に命を賭けた人間」として再考する。
第1章:酒と泪と、誤解と真実──「酒飲みの歌」の代償?
「酒と泪と男と女」──
1976年に発売され、いまも多くの人が口ずさむこの歌によって、河島英五は“酒を愛する男”の象徴となった。
- ラジオでも酒の話が多かった
- ステージでも日本酒やビールを飲みながら歌うスタイルが話題に
- 「豪快」「人情」「酔いどれブルース」──そんな言葉がぴったりの歌声
しかしそのイメージが強すぎたのか、2001年に48歳という若さで亡くなった際も、
多くの人はこう思ったはずだ。
「酒の飲みすぎで早死にしたんだろう」
──だが、それは真実ではない。
河島英五の死は、もっと静かで、長い闘病の果てにあった。
第2章:C型肝炎──静かに進行していた「見えない病」
河島英五さんの直接の死因は、アルコールの過剰摂取ではなく、
C型肝炎ウイルスによる慢性的な肝疾患──そしてそれに伴う肝硬変だった。
■ いつ感染が分かったのか?
1980年代半ば、すでにC型肝炎ウイルスへの感染が確認されていた。
当時はまだC型肝炎の治療法が乏しく、インターフェロン治療も一般化しておらず、
感染=慢性化=いずれ肝硬変や肝がんへ進行、という時代だった。
つまり河島さんは、「歌のイメージ」とは裏腹に、
20年近くもの間、静かに“肝臓の時限爆弾”と共に生きていたことになる。
■ お酒をやめていたという証言
イメージに反して──
彼は病気が判明してから、
- タバコをやめた
- お酒も基本的には飲まず、打ち上げの乾杯程度
- ステージ裏では、ビールの代わりにお茶を飲んでいた
という証言が複数残されている。
「酒を愛する男」が、“酒を断ちながら、それでも歌い続けていた”。
この静かな決意は、表には出てこなかったが、深いものがあった。
第3章:吐血、入院、そして…それでも「歌うことを選んだ」
2000年の年末。
河島英五さんの身体は、静かに、だが確実に限界に向かっていた。
■ 吐血から始まった急変
2001年1月、彼は突然吐血して救急搬送される。
検査結果は──
- 肝硬変
- 食道静脈瘤の破裂寸前
- 重度の肝機能低下
本来であれば、即座にステージを降りて静養すべき状況だった。
しかし彼は、違った。
■ ステージに立ち続けた男
医師の制止を振り切るように、彼はこう言ったという。
「歌ってる間は、病気が逃げていくんです」
そして、体調が思わしくない中でも──
- ライブに出演
- 観客の前でフルセットを歌唱
- 楽屋では酸素ボンベを手放せなかった
亡くなるわずか2日前まで、彼はステージに立っていた。
それは、命を削るような“最後の熱唱”だった。
人々が「酔いどれの詩人」だと思っていたその時、
実際には「歌で命を繋いでいた人」だったのかもしれない。
第4章:「酒と泪と男と女」は、誰よりも静かに“禁酒”した男が歌っていた
世間は“酔いどれ詩人”として彼を見ていた。
だがその実、河島英五さんは──
誰よりも酒を慎み、病と闘いながら歌を全うした男だった。
■ 音楽は「生き様」の代弁だった
「酒と泪と男と女」はたしかに酒の歌だ。
だがそれは、ただの飲んだくれの歌ではない。
- 泣いて、酔って、それでも立ち上がる人間の歌
- 感情の泥濘(ぬかるみ)を抱きしめるような詩
- 哀しみや弱さを“共感”へ変える力があった
そして彼自身、“病気と付き合いながら生きること”を、
この歌の精神そのものとして実践していた。
■ 「酒」を語りながら、「お茶」を飲んでいた男
打ち上げでグラスを持ち、「カンパーイ!」と笑っていた河島さん。
その中身がお茶だった──というエピソードは、どこか切なく、どこか優しい。
豪快な笑顔で、
禁酒の苦しみも、肝臓の痛みも見せずに、
人前では「歌う河島英五」であり続けた。
イメージと真実の間で、最も静かな闘争をしていたのは、彼自身だったのかもしれない。
第5章:歌は生きた、彼の命が尽きるその日まで──そして私たちが受け取ったもの
2001年4月16日、河島英五さんは息を引き取った。
48歳──あまりにも早い別れだった。
だが、その最期の瞬間まで彼は、
“歌いながら、生きた”。
■ 観客が見ていたのは「声」ではなく「魂」
亡くなる2日前に出演したライブでは、すでに歩くのもままならなかった。
それでもステージに上がると、声が出た。
笑顔もあった。観客を魅了する“いつもの河島英五”が、そこにいた。
- 声量が少し落ちても
- 痩せていても
- 病気を隠すように、語らず
歌の中に、彼の命があった。
まとめ:「酒と泪」のイメージを越えて
河島英五さんは「酒を愛しすぎた男」ではなかった。
正確に言えば、“酒を愛していた過去”を持ちながら、それを制限し、病と共に歌い抜いた人”だった。
- 有名な「飲んべえソング」の背後に、禁酒生活があった
- “酔いどれキャラ”のまま亡くなったわけではない
- 実際はC型肝炎と20年にわたる闘病の末に倒れた
- 最期の最期まで、歌いながら生きることを選んだ
その姿はまさに、
「歌を生きた人」「生を歌った人」と呼ぶにふさわしい。

「“酒の歌”の向こうに、こんな静かな闘いがあったなんて…胸が震えたブー…」
「河島さん、あんたはやっぱり“本物の男”だったブー」



















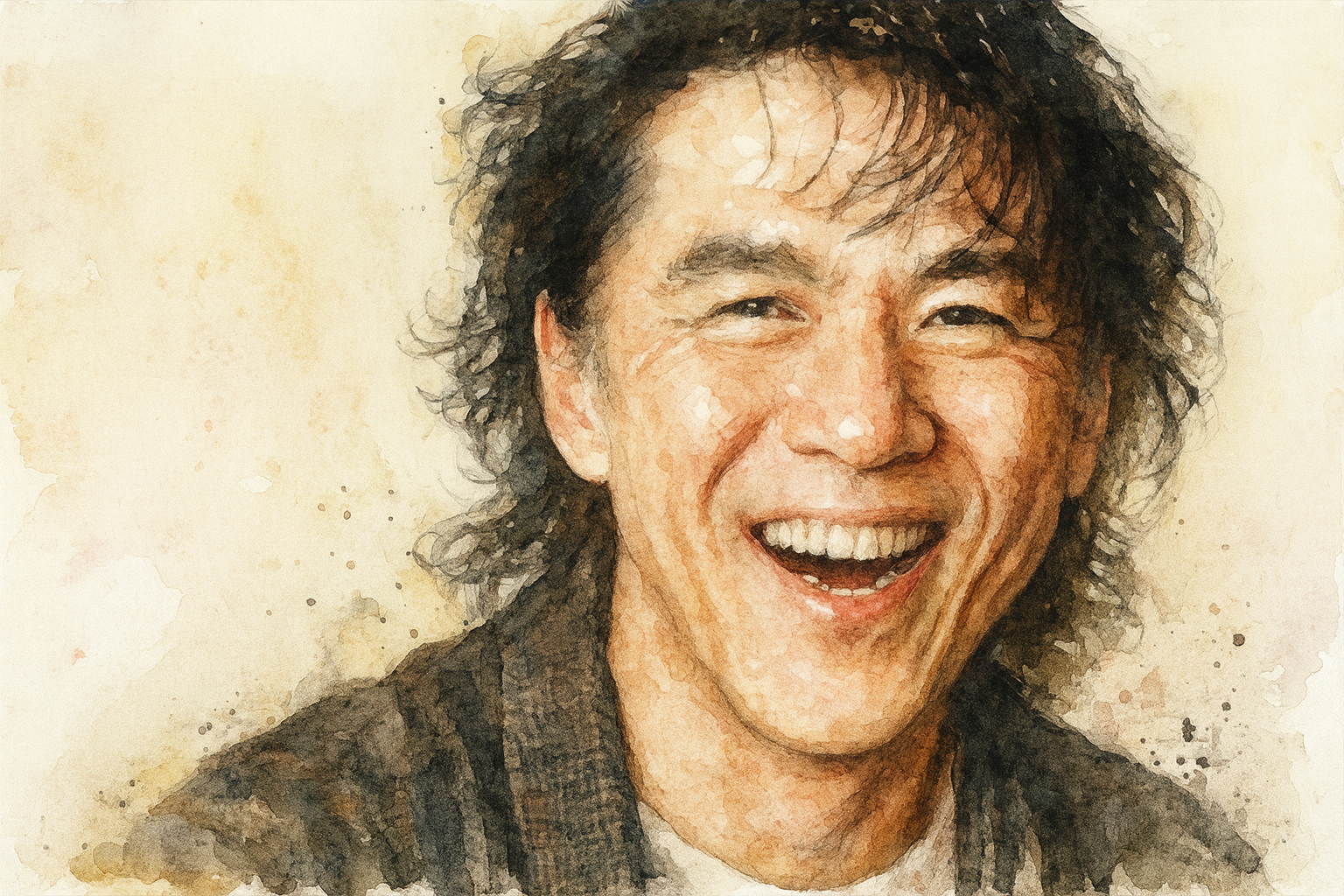


コメント