「辞めたい」と言えない時代の“救世主”として急成長した退職代行サービス。
その代表格とされた「モームリ」に突如として家宅捜索のメスが入った。
キーワードは「非弁行為(ひべんこうい)」──。
法律の素人が、法律家の領域にどこまで踏み込めるのか。
これはただの「代行」なのか、それとも違法な「代理」なのか。
背景には、複雑化する雇用現場と、グレーゾーンを見逃してきた業界構造がある。
本稿では、“モームリ事件”の全貌を追いながら、
退職代行という「使いやすさ」と「法の限界」の間に横たわる深い問いを掘り下げていく。

「どんどん人気が出てただけに、“えっ、あそこに家宅捜索?”ってビックリしたブー…!」
第1章:「退職代行」という名の越境──モームリに迫った“非弁捜査”の衝撃
「もうムリです」──その一言が「モームリ」の名前の由来である。
SNSやYouTube広告で若年層の共感を集め、たった2年で4万人以上に使われた退職代行サービス「モームリ」は、あまりにも急速に浸透していった。
そんな“新時代の救世主”に、突如として家宅捜索のメスが入ったのは2025年10月22日。
警視庁が入った容疑は、「非弁行為(ひべんこうい)」──弁護士法違反である。
■「非弁行為」とは何か?
法的に定められた「非弁行為」とは、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務を代理、またはあっせんする行為。
つまり、退職代行業者が本人に代わって会社と法的な交渉を行ったり、弁護士に交渉を委託し、その紹介料を得たりする行為が該当する。
東京弁護士会はこの点について、2024年にすでに警鐘を鳴らしていた。
「残業代未払い」や「パワハラ慰謝料」などを含む“交渉”に業者が介入することで、依頼者が本来得るべき権利を取り損ねるリスクがあるというのが、非弁規制の根幹にある理念だ。

「まるでお医者さんじゃないのに手術しちゃう、みたいなイメージだブーね…」
■ モームリは“紹介料1万6500円”のノルマ?
今回の強制捜査では、「モームリ」運営元の株式会社アルバトロスと提携弁護士事務所など、複数拠点に100人規模で家宅捜索が行われた。
疑われたのは、弁護士への退職業務あっせんと、それに対する報酬の受け取り。
元社員の証言によれば──
「弁護士に紹介すれば1万6500円が会社に入る、ノルマだ、と社長が皆の前で言っていた」
「違法な行為だと認識しつつ、『会社外では絶対口外するな』と言われていた」
──など、組織的・反復的な非弁あっせんの実態が浮かび上がっている。
さらに社内は「誰かが誰かのミスを探しているような空気」で、プレッシャーに満ちた労働環境だったとも証言された。

「ウワァ…そんな“公開営業目標”みたいに言われたら、やらざるを得ない空気になっちゃうブーよね」
■ 「代行」と「代理」はどこで分かれるのか?
利用者から見れば「退職を伝えるだけ」だとしても、実際にはその線引きは曖昧だ。
会社から「理由の説明を求められた」「有給をずらしてくれと言われた」「退職金は払わない」といった“交渉”の場面が発生したとき、代行業者がそれに応じた瞬間、「代理」=弁護士の独占領域に踏み込んでしまう。
サービスの紹介動画でも、
「会社には有給の時期変更権はありません」
「残業代の計算は会社でして振り込んでください」
といったやりとりが交わされており、法的解釈を含む“交渉”と見なされるリスクがある。
■ 「グレーゾーン」のまま広がった構造
この構造は、「非弁」問題が指摘されながらも、長らく放置されてきた結果でもある。
そもそも、退職代行というジャンル自体がここ数年で急成長した新領域だ。法律と実務の間には温度差があり、明確な線引きを怠ったまま“とりあえずOK”で広まってしまった。
法的知識に疎い利用者と、成果報酬を追う運営者が結びつけば、本来の権利が損なわれる可能性が高くなる。
「医師でない者が手術をすることは許されないように、弁護士でない者が交渉をしてはならない」──それが非弁の理念であり、法の守るべき最低限のラインなのだ。

「“気軽なサービス”の裏側には、“本来守られるべきルール”があるってことだブーね…」
第2章:誰が守ってくれるのか?──非弁行為に潜む“無自覚な損失”
退職代行というサービスは、確かに心理的ハードルを下げた。
「出社せずに退職できる」「上司と一切話さなくて済む」──そんなキャッチコピーに救われた若者は少なくない。
しかしその裏で、気づかぬまま“損”をしている人も確実に存在する。
なぜなら、「退職の意思を伝えるだけ」では済まない場面が、現実には多数存在するからだ。
■ 交渉の余地を失うことの重大さ
- 残業代の未払い
- 退職金の未提示
- パワハラによる慰謝料請求
- 有給消化の拒否
- 離職票の遅延や不備
これらは、“言わなければ通らない”。
だが、非弁リスクを避ける業者は交渉を行えない。
逆に“グレー”を突き進む業者は、間違った交渉や不当な示談を行う可能性すらある。
どちらにせよ、依頼者本人が「何を失ったか」に気づかないまま、退職は完了する。
これは、沈黙の中で進行する損失であり、極めて深刻な人権リスクなのだ。
ここでよくある誤解が、「弁護士と提携していれば安心」というもの。
確かに「ガーディアン」など弁護士法人が運営する退職代行は合法だ。
だが、「一般業者が顧客を弁護士にあっせんし、紹介料を受け取る行為」は、明確な非弁違反となる。
◯【合法な連携】
・顧客が自分で弁護士に依頼する
・運営元が弁護士資格を持つ法人である
✕【非弁の可能性がある】
・弁護士に「顧客を紹介」し、紹介料を受け取る
・交渉を前提としたあっせんや業務共有を行う
非弁問題は、裏で「誰が利を得ているか」を見れば、ほぼ判別がつく。
■ なぜ“グレー業者”が広がったのか
構造的には、こうだ。
- 若者の退職心理は“脱出口”を求めていた
- メディアやSNSで拡散され、マッチングアプリのような感覚で「辞めたい」が拡張された
- 法律リテラシーの空白地帯を突いて、事業者が乱立
- ユーザーは「安さ」や「早さ」で選び、リスクに気づかない
- 一方で、まともな弁護士系サービスは価格競争で不利に
つまり、「正攻法が損をする」構図が放置されていたのだ。
第3章:なぜ今、強制捜査だったのか──“退職の自由”を守るために
退職代行「モームリ」への家宅捜索──。
この報道に驚いた人は多いはずだ。
なぜなら、退職代行サービスは「広く認知された安心ツール」として、すでに一定の社会的地位を得ていたからだ。
しかし今回、警視庁は異例の約100人態勢での一斉捜索に踏み切った。
それは一体、何を意味するのか?
■ 「非弁」の枠を超えた、“ビジネスモデル”の疑惑
今回の容疑は、弁護士法72条違反。
その中でも特に問題視されたのが「弁護士への仕事のあっせん」と「報酬の授受」だ。
報道によれば、モームリでは──
- 弁護士に案件を紹介し、1件あたり1万6500円の報酬を受け取っていた
- 社内で社員に「弁護士に紹介すれば売上になる」と伝えていた
- 違法性を認識しながら「外では口にするな」としていた
…とされている。
つまりこれは、“無資格での交渉代行”という単なる非弁問題ではなく、
組織的に非弁行為を収益化するスキームが構築されていた可能性を示している。

「“紹介してお金もらう”って、うっかりやってしまいそうだけど、法律ではNGなんだブー…」
■ 「やってはいけない」の“重さ”
非弁行為とは、単なる法律違反ではない。
たとえるなら、
- 医療資格のない者が、患者の手術を代行して報酬を受け取る
- 無免許の人が、公共のバスを運転して運賃を得る
こうした行為と本質的に同じであり、
本人が気づかないうちに不利益を被る構造を生み出す、極めて危険な問題なのだ。
■ 「モームリ」の特殊性:なぜ注目されやすかったのか?
今回の件が注目を集めた背景には、いくつかの“特殊要因”がある。
- SNSマーケティングでの知名度急上昇(サービス開始からわずか数年で4万人超の利用者)
- 「辞めたきゃ辞めろ」のシンプル訴求が若者に刺さった
- 代表のキャラクター性や、過激な発言もメディア露出の加速要因に
- 価格競争による“安さ”と“即時性”の魅力
- 退職理由を巡る人々の“共感ストーリー”(例:「タイピング音がうるさい」など)
つまり、“辞めたい人の味方”という社会的ポジションを構築することに成功していた分、
疑義が発覚した際の衝撃は大きく、社会的影響も大きかったのだ。
第4章:それでも「退職代行」は必要か?──分水嶺に立つサービスの未来
今回の家宅捜索は、退職代行業界全体に大きなインパクトを与えた。
だがここで、冷静に立ち返って考えるべき問いがある。
それは──
「そもそも退職代行サービスは必要なのか?」
という根源的な問いだ。
■ 退職は“誰にでも認められた権利”のはずなのに…
本来、会社を辞めることに、弁護士も上司の許可も必要ない。
民法上のルールでは、2週間前に申し出れば、労働者にはいつでも辞める自由がある。
にもかかわらず、退職代行サービスがここまで普及した背景には、
企業側の“心理的な引き止め”や“慣習的圧力”が依然として残っている現実がある。
- 「今辞めたら迷惑がかかるだろ」
- 「社会人として非常識だぞ」
- 「退職理由を説明しないと認めない」
…こうした言葉が「合法的圧力」として使われ、
辞める自由を奪われている人が確実に存在している。
■ テクノロジーで“人間関係”を代行する矛盾と必要性
退職代行とは、突き詰めれば“人間関係の断ち切り”の代理だ。
- 「言いにくいことを、誰かに代わりに言ってもらう」
- 「嫌な顔を見ずに、関係を断ちたい」
そんな現代の働き方とメンタルヘルスの問題に、テクノロジーと外部サービスが応えようとした試みとも言える。
つまり、退職代行の存在意義自体を否定することはできない。
必要としている人が、確かにいるからだ。
■ 必要なのは“安心して使える仕組み”の整備
今回の問題で可視化されたのは、業界の制度的な整備の遅れでもある。
現在、退職代行サービスには法律上の明確な資格要件やルールが存在せず、
弁護士・労働組合・民間企業が入り乱れたグレーな構造のまま市場が拡大してきた。
今後は以下のような方向性が求められるだろう。
- 弁護士による退職代行の明確なルール整備
- 「非弁行為」か否かをめぐる基準の明確化
- 利用者保護の観点からの第三者チェック機構の設立
- 透明性ある料金・業務説明の徹底
これにより、「安心して使える退職代行」という本来の目的が守られ、
本当に必要とする人たちが泣き寝入りせずに済むようになる。
終章:あなたの“退職の自由”を守るために──信頼されるサービスのあり方とは
■ 「辞める自由」は、“働く自由”と表裏一体である
私たちは「働く権利」を尊重する社会に生きている。
だが本来、それは「辞める権利」と不可分のはずだ。
- どんな理由であれ、自分の人生をリセットする権利
- 誰にも縛られず、離れる自由
- 精神的・肉体的な危機から自らを守る選択
これらはすべて、「退職」という言葉に込められた、人間らしい自己決定の一形態だ。
そしてこの当たり前の自由を守るには──
「辞めます」と言えない人を責めるのではなく、守る社会の仕組みが必要なのだ。

「“辞める自由”を奪われるって、すごく怖いことだブー…」
■ グレーゾーンの中で問われるのは、誠実さと透明性
今回の「モームリ」事件が物語るのは、単なる法違反の有無ではない。
それは、急拡大する“人の心の隙間”に入っていった新ビジネスが、
誠実さや法的な裏付けを怠れば、すぐに信頼を失うという教訓でもある。
誰かの人生の岐路を支えるのならば、
そこにあるべきは、技術やノウハウではない。
信頼と説明責任、そして人を尊重する視線だ。

「“まじめにやってるところ”まで疑われたら悲しいブー…。信頼って、一瞬で揺らぐものだブー…」
■ これから私たちがすべき問いかけ
- 「誰が、どの立場で、どこまでできるのか?」
- 「依頼者の“本当の希望”は何なのか?」
- 「その行動は、依頼者を守ることになっているか?」
これらの問いを、退職代行業者も、弁護士も、社会も、真剣に自問すべき時に来ている。
■ “泣き寝入り”でも、“違法ビジネス”でもない、第三の選択肢を
退職代行サービスは、決して悪ではない。
しかし、無法地帯になってはならない。
必要なのは、
- 利用者が安心して頼める仕組み
- 透明なルールの上で健全に運営される市場
- そしてなにより、「働く人の自由を守る」という理念に忠実なプレイヤー
この三つが揃って、初めて退職代行は
“社会にとって本当に意味ある仕組み”になれるのだ。
■ そして、次の物語へ──
「辞めたい」と言えなかったあなた。
「言ったけど、聞いてもらえなかった」あなた。
「代行を使ってまで辞めたいほど、苦しかった」あなた。
そんなすべての人に、こう伝えたい。
あなたの選択に、罪はない。
大切なのは、その後の歩みだ。
自分を取り戻す一歩目としての“退職”が、
誰にも否定されない世の中になりますように。

「“辞める”って、自分を取り戻すための第一歩かもしれないブー!」



















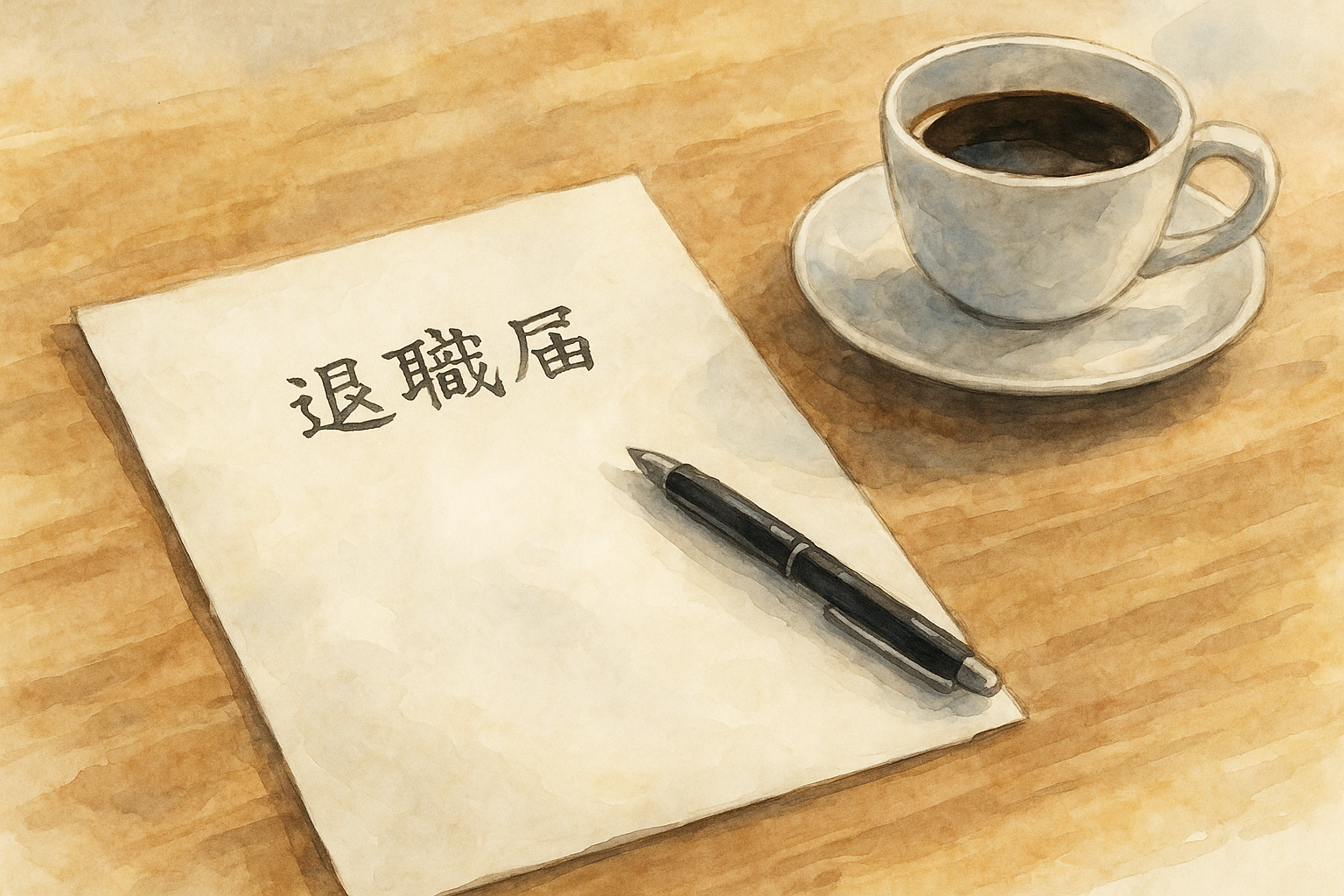
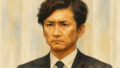

コメント