「番号で言ってもらえますか?」
コンビニでタバコを注文した際、そう言われてキレる人がいる──2025年8月、東京近郊のコンビニで起きた一件がSNSで話題になった。
銘柄で注文した客に対し、店員が「番号でお願いします」と対応。
それが気に食わなかったのか、客が大声を上げて激怒する“逆ギレ”事案に発展した。
しかし今や、タバコを番号で注文するのは業界共通ルール。
そもそも「その銘柄を知らない人」が増えている現代において、銘柄注文が通じない=店員が悪いとは言えないはずだ。
本記事では、この“ささいな苛立ち”の背景にある構造的ズレを考察していく。
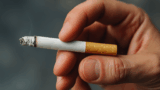

第1章:いま、タバコは「番号で注文する」が常識
コンビニでのタバコ販売では、各銘柄に番号が振られている。
たとえば、「メビウス・オプション・パープル・5・100’s」は「63番」のように、
“番号札方式”でのオーダーが原則となっている。
これは…
- 銘柄の種類が膨大(100種類以上)
- パッケージが似ていて間違えやすい
- 店員が喫煙者とは限らない
という現場事情をふまえた“合理的ルール”だ。

「タバコの名前って長いしややこしいし、全部覚えろって無理あるブー…
番号って「みんなのための共通語」なんだブー!」
第2章:「銘柄が通じない」ことにキレる心理
今回のように「銘柄を伝えたのに通じなかった」とキレる人は、
“サービス提供側が自分に合わせるべき”という前提を持っていることが多い。
そこには、次のような心理が潜んでいる。
→ 昔のコンビニでは銘柄名で通じた。だから今でも通じるべきという思い込み。
→ 「誰でもこの銘柄くらい知ってるだろ」という視点の偏り。
→ 店員の態度が気に入らないのではなく、「通じなかった事実」に怒っている。
こうした心理が重なると、「なんでわかんねぇんだよ」という
非合理な“怒りの爆発”が起こる。
第3章:そもそも、今は「タバコの銘柄なんて知らなくて当たり前」
重要なのは、喫煙率の低下とコンビニ店員の多様化。
- 男性:ピーク時(1960年代)で80%以上 → 現在は25%前後
- 女性:10%以下を維持
- 若年層では「喫煙経験ゼロ」が多数派に
つまり「タバコを吸ったことがない人」がマジョリティに近づいている。
さらに、
- 外国人スタッフ
- 高校生・大学生のバイト
- タバコに興味ゼロな非喫煙者
が多く働くコンビニ現場で、
“◯◯ライトの5mg”みたいな銘柄をすべて暗記して対応しろ”というのは、無茶な要求だ。
第4章:「タバコを買う」ことに、もう“気遣い”が必要な時代
ここに来て、喫煙者側のマナーが問われている。
→ 覚えられないならスマホで写真 or 空箱を見せる
→ 銘柄注文は「通じたらラッキー」くらいの姿勢で
→ 高級ホテルじゃない。時給バイトに過剰期待しすぎない
こうした“配慮”が求められる背景には、
「タバコ=特別扱いされるものではなくなった」という価値観の変化もある。

タバコ買うときって、「買わせていただく」くらいの心づもりがちょうどいいブー…
そうすればトラブルなんて起きないブー!
第5章:これは「タバコの話」じゃない。“伝わらない時代”の話だ
今回の事例は、タバコの話に見えて、実は「常識のズレが怒りを生む構図」の縮図でもある。
- 昔は通じたことが今は通じない
- 自分のルールが、相手には無関係
- そのギャップに気づけない人が怒る
こうした現象は、
電車の席取り・スマホの使い方・お会計時の言葉遣いなど、
日常のあらゆる場面で起きている“すれ違い”でもある。
今回の“タバコ銘柄事件”は、それを象徴する出来事だったと言えるだろう。
まとめ:「番号で言ってください」の裏にある“文化の変化”
コンビニ店員が「番号でお願いします」と言ったとき、
それはマニュアルではなく、“時代の要請”でもある。
銘柄で伝えて怒る人は、その変化に気づけないまま、
「自分の常識が通じない世界」に怒っているのかもしれない。
しかし本当に怒るべきなのは、
「伝わらない相手」ではなく、「アップデートできていない自分自身」なのではないか。

「銘柄が通じない=怒る」って、もはや“旧時代の象徴”だブー…
タバコの煙だけじゃなくて、思い込みもそろそろ“分煙”してくれだブー!






















コメント