お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎(50)。
かつて「M-1」や「THE SECOND」で見せた豪快な漫才からは想像もつかない、過酷な闘病の道を歩んでいた。
新型コロナ感染による意識不明、人工透析、腎移植の失敗、敗血症性ショック──。
そして2025年9月、彼は左足を膝上から切断する決断を下した。
それでも、笑いをやめなかった。
有吉弘行がラジオで語った「二郎さん、足を切ったんですよ」という一言は、日本中に静かな衝撃を走らせた。
しかしその裏には、“生きるための決断”と“芸人としての矜持”があった。
本稿では、ハチミツ二郎を襲った病の医学的背景と闘病の記録をもとに、
「命を賭けて笑いを届け続ける男」の軌跡を辿る。
第1章:敗血症がもたらした「足の壊死」──命を救うための決断
2025年9月。
ハチミツ二郎は再び、生死の境に立っていた。
入退院を繰り返していた彼の左脚は、もはや「足」としての形を保てなくなっていた。感染は筋肉や皮膚を蝕み、血管を詰まらせ、医師はついに口を開いた。
「このままでは命が危険です。切るしかありません」
その診断は、芸人としてのキャリアよりも先に、「人間として生き延びるか否か」を問う最終通告だった。
■ 感染の連鎖:膿瘍から敗血症へ
すべての始まりは、2023年夏に発症した左大腿会陰部筋肉内膿瘍だった。
筋肉の奥深くに膿が溜まり、細菌が血流に乗って全身へと拡散。結果、彼は敗血症性ショックに陥る。
敗血症とは、感染が全身に波及し、臓器障害を引き起こす極めて危険な状態だ。血圧が急低下し、腎臓や心臓が機能不全に陥る。
ハチミツはその瞬間、「医者が家族を呼ぶ」ほどの危篤状態にまで追い込まれていた。
「生きているのが不思議だった」
――本人が語ったその一言が、当時の壮絶さを物語る。
この感染は一度は沈静化したものの、体の奥底に残った火種が再び炎上した。
感染が再発し、壊死が進行していったのだ。
■ 壊死が意味するもの
壊死とは、細胞が完全に死滅し、再生不能となる状態を指す。
組織は黒く変色し、悪臭を放ち、感染の温床となる。
通常であれば、抗菌薬や手術で壊死部分を切除すれば回復する。
だが、ハチミツの場合は違った。
糖尿病と人工透析という二つの要因が、治癒力を大幅に奪っていた。
- 糖尿病により血流が悪化し、酸素や栄養が届かない
- 透析による免疫低下で、感染への抵抗力が落ちている
結果、膿瘍は次第に再燃し、皮膚や筋肉の再生は不可能となった。
医師団は最終的に、感染の拡大を食い止める唯一の方法として「切断」を選んだ。
■ 「命を取るか、足を取るか」
ハチミツはこの決断の瞬間、ため息すらつかなかったという。
苦悩よりも先に、「これでようやく終わるかもしれない」という安堵の方が勝っていたのだ。
「足はなくなったけど、命が残った。
これで笑えるようになったら、それでいいんだよ」
9月中旬、左膝上からの大腿切断手術が行われた。
感染は止まり、敗血症の再発も防がれた。
しかし、その代償はあまりに大きかった。

「足を失っても“笑い”は切れなかったブー…。
命を救うための“ツッコミ”みたいな決断だブー…。」
ここに至るまでに、ハチミツ二郎の身体には、数えきれないほどの闘いがあった。
第2章:コロナと腎不全──透析が始まった日
2021年初頭、冬の東京。
ハチミツ二郎は、いつものようにステージに立ち、客席を笑わせていた。
その数日後、突然高熱と倦怠感に襲われ、検査の結果は新型コロナ陽性。
そして、この感染が彼の運命を大きく変えることになる。
■ “死の8日間”──意識を失ったICU
感染から数日後、急激に体調が悪化。
呼吸が乱れ、酸素飽和度が急落。救急搬送された彼は集中治療室(ICU)で8日間意識不明となった。
医師の説明によれば、肺炎だけでなく腎臓が急性機能不全を起こしていた。
つまり、コロナウイルスの全身感染が腎臓の毛細血管を破壊し、急性腎障害(AKI)を引き起こしていたのだ。
目を覚ましたとき、彼の首には管がつながり、腕には点滴。
そして下腹部には透析用カテーテル。
医師は静かに告げた。
「あなたは助かりました。ただし、腎臓はもう元に戻りません」
■ 人工透析という「第二の人生」
それ以来、彼は週3回の人工透析を続ける生活に入った。
1回あたり4〜5時間。
血液を体外に出して浄化する過酷な治療だ。
コロナの後遺症で息切れが残り、免疫力も著しく低下。
体は常に疲弊し、透析のたびに体重が増減し、低血圧で倒れることもしばしば。
それでも彼は、ステージに立ち続けた。
「透析後に漫才をやると、笑いよりもまず“息継ぎ”が先に来る」
と冗談交じりに語っていたが、
その実、体は常にギリギリの状態だった。
■ コロナが奪ったものと、残したもの
医師たちは彼に「仕事を減らすように」と忠告したが、
ハチミツは言葉を詰まらせたという。
「笑うことしか、できないから」
コロナは彼の腎臓を奪った。
だが同時に、「生きること」そのものを意識させた出来事でもあった。
人工透析は確かに束縛だ。
だが、週に3日、自分の命が機械によって保たれているという事実が、
彼にとって“生きている証拠”でもあった。
「死んだと思った。だから今は、笑ってるだけで十分なんだよ」
その言葉は、もはや芸人のネタではなかった。
生還者としての実感そのものだった。

「コロナが腎臓を奪っても、“笑い”は残ったブー…。
命をつなぐチューブが、彼にとって“マイク”だったブー…。」
第3章:母の腎臓に託した希望──生体移植の失敗
2023年3月。
長く続いた透析生活の先に、ようやく一筋の光が差していた。
それが――母親をドナーとした生体腎移植だった。
■ 「母ちゃんの腎臓なら、きっと元気になる」
透析生活が2年を超え、ハチミツ二郎はすでに芸能活動をセーブしていた。
週3回の通院。体重・塩分・水分、すべてを厳しく制限された日々。
そんな中で、母親が静かに言った。
「私の腎臓、あげるよ」
それは親としての本能だった。
二郎は一度は拒んだ。
しかし、娘の父である自分が倒れれば、家族はどうなる。
その思いが、ついに決意を変えた。
2023年春、母子は共に入院。
東京の大学病院で、生体腎移植の手術に挑んだ。
■「手術は成功しませんでした」
当初は順調に見えた。
だが、数日後、医師が告げた言葉は冷たかった。
「手術は成功しませんでした」
新しい腎臓は拒絶反応を起こし、機能しなかったのだ。
本来なら、母の腎臓が二郎の体に馴染み、透析から解放されるはずだった。
しかし、彼の体はそれを受け入れなかった。
再び透析が始まり、長期入院へ。
手術は成功しなかったが、母親は「息子の命が繋がっただけでいい」と涙を流したという。
■ “希望が崩れる音”と芸人のプライド
この失敗は、精神的にも大きな打撃だった。
漫才トーナメント「THE SECOND」へのエントリーも辞退。
彼は自らのnoteにこう綴った。
「また病院かよ、って自分でも笑っちゃう。
でも、笑わないと心が腐っちゃうんだ」
芸人としてのプライドが、心を支えていた。
舞台には立てない。
だが、ベッドの上でも“笑い”を忘れなかった。
「透析中にネタを考えてると、血が洗われる音がリズムになる」と話していた彼らしいユーモアは、
生きるための“自己治療”でもあった。

「お母さんの腎臓で“命のリレー”だったブー…。
失敗しても、その想いはちゃんと生きてるブー…。」
第4章:再び敗血症に──壊死と向き合った日々
2023年8月。
腎移植の失敗から数カ月。
ハチミツ二郎の体を再び、感染が襲った。
左脚の付け根から大腿にかけて、ズキズキと焼けるような痛み。
高熱と悪寒、そして全身の倦怠感。
病院に駆け込んだ彼を待っていた診断は――
「左大腿会陰部筋肉内膿瘍」および「敗血症性ショック」。
■ 命を奪う「静かな爆発」
筋肉内膿瘍とは、体の深い層に細菌が侵入して膿が溜まる病気だ。
だが彼の場合、それが「透析患者」であることによって事態は一変した。
人工透析によって腎臓の機能を代替している身体は、
免疫力が著しく低下している。
細菌に対する抵抗力が弱まり、血液の浄化が追いつかない。
膿瘍はやがて血流に乗って全身へ拡散。
敗血症性ショック――感染が全身に波及し、
血圧が急激に低下、臓器が次々と悲鳴を上げる。
医師は家族を呼び、
「もう覚悟を」と伝えたという。
だが、ハチミツは今回も笑いながら生還した。
死線をくぐり抜けた男は、
ICUから出ると看護師にこう言った。
「また生き返っちゃったよ。
これ、もうポイントカード作った方がいいね」
■ 長引く入退院、そして壊死との戦い
敗血症は奇跡的に克服したが、
その代償として彼の左脚には深いダメージが残った。
筋肉の一部が壊死し、皮膚の血流も悪化。
一見治ったように見えても、内部で細菌が燻っていた。
壊死した組織は、時間が経つごとに腐敗し、
再び感染源となる。
「ドレナージ」と呼ばれる膿の排出処置を繰り返しても、
完治には至らなかった。
透析による免疫低下、糖尿病による血管障害、
そして感染による組織壊死――。
複数の病態が複雑に絡み合い、
「もう足を残すのは限界」という結論に近づいていった。
■ 「切ること」が救うことだった
医師の判断は厳しかったが、
彼自身も理解していた。
「この足がある限り、
また同じことを繰り返す」
感染を根絶するには、壊死部を完全に取り除くしかない。
そして、その範囲は膝上に及んでいた。
「命を取るか、足を取るか」。
それは冷たい選択肢だったが、
彼は迷わなかった。
「切るのは足だけでいい。
笑いは切らない」

「“切断”じゃなくて、“再生”の始まりだったブー…。
だって彼の笑いは、どこも腐らなかったブー…。」
第5章:膝上切断の決断──命をつなぐ“最後の手術”
2025年9月、夏の終わり。
病室に響いた医師の声は静かだった。
「左足を、膝の上で切断します」
その言葉を聞いた瞬間、ハチミツ二郎はうなずいた。
驚きも、涙もなかった。
心のどこかで、もう覚悟は決まっていたのだ。
■ 「ここで切らなきゃ、もう助からない」
彼の左脚は、もはや自分の一部とは言えなかった。
壊死した筋肉は黒ずみ、血流はほとんど途絶えていた。
皮膚を通じて感染が広がり、体は再び敗血症の危険に晒されていた。
医師たちは言った。
「ここで切らなければ、次に壊死するのは内臓です」
ハチミツは、淡々と答えた。
「わかりました。やりましょう」
命を守るために足を差し出す――
その決断は、痛みや恐怖を超えた“理性”の産物だった。
■ 手術は成功、命のリスタート
手術は数時間に及んだ。
左膝上から大腿の中ほどまでを切断し、
感染源となっていた組織をすべて取り除いた。
麻酔から目覚めたとき、彼は静かに呟いた。
「あぁ、生きてるな」
命の危機は脱した。
しかし、痛みは凄まじかった。
いわゆる幻肢痛――失った足がまだ“ある”と錯覚し、
そこに痛みを感じる現象が彼を苦しめた。
夜中、何度もうなされながらも、
「この痛みは、生きてる証拠」と笑っていたという。
■ 有吉弘行が語った“真実”
10月5日、有吉弘行のラジオ番組「SUNDAY NIGHT DREAMER」で、
有吉は突然こう切り出した。
「ハチミツ二郎さん、足を切りました」
スタジオは一瞬、静まり返った。
有吉は続けた。
「詳しくは本人のnoteに書いてある。
有料だけど、それだけの価値はあるよ」
そしてこう付け加えた。
「足を切る切らないって、すごくセンシティブだけど、
それで気持ちも軽くなったんだと思う」
“足を切った”という言葉に込められたのは、
悲劇ではなく、再生だった。
有吉は冗談めかしてこう言った。
「みんなで金集めて、いい義足作ろう。
火が出たり、ナイフが仕込んであったりしてさ」
それを聞いたリスナーは笑い、泣いた。
“笑い”が再び、命のリハビリを始めていた。
■ 明るく受け止めた仲間たち
共演者のタイムマシーン3号・関太は、見舞いに行った際のことを語った。
「『切っちゃったよ』って、転んだみたいなテンションで言うんです。
冗談かと思うくらい明るかった」
芸人仲間たちは口を揃えて言う。
「二郎さん、もう一回舞台に立つよ」
■ 義足と、娘と、これから
術後、彼はリハビリを開始した。
義足の装着を目指しながら、
再び「舞台に立つ」夢を見据えている。
そして、noteに綴った言葉。
「足はなくなったけど、
娘に“父ちゃん、生きてるよ”って言えるのが一番の誇り」
足を失っても、芸を失わない。
命を削っても、笑いを捨てない。
その姿勢こそが、ハチミツ二郎という芸人の真骨頂だった。

「切ったのは“足”じゃなくて、“過去の痛み”だブー…。
ここから、ほんとの“二郎リスタート”だブー…」
最終章:義足のステージへ──“笑い”で命を繋ぐ
病室のカーテンを揺らす光の中、
ハチミツ二郎はリハビリ室で静かに立とうとしていた。
左膝上まで切断された足に、まだ新しい義足を装着する準備をしている。
■「足がなくても、ステージはある」
術後数週間。
彼はnoteにこう綴った。
「足はないけど、またステージに立ちたい。
義足でもいい、いや、義足だからこそ見える景色があるはずだ」
その言葉には、敗北ではなく挑戦の響きがあった。
義足のリハビリは想像以上に過酷だ。
装着面が擦れ、炎症が起きる。
歩くたびに幻肢痛が走る。
それでも彼は、笑いながらこう言ったという。
「ほら、今度は“鉄のツッコミ”ができるじゃん」
■ 笑いで命を繋ぐという生き方
ハチミツ二郎の生き様は、病との闘いではなく、笑いとの共生そのものだった。
「死の8日間」を経て人工透析となり、母親の腎臓を移植しても失敗し、
足を失ってもなお、人前で「切っちゃったよ」と笑える。
彼にとって“笑う”ことは、治療でもあり、祈りでもあった。
医師が諦めた夜も、
透析の音をリズムにネタを考えた朝も、
すべてが「生きてる実感」を形にする行為だった。
「病気に負けたら、笑いも死ぬ。
だから、笑ってる間は、まだ勝ってる」
■ 娘に見せたい背中
ハチミツ二郎には、12歳の娘がいる。
母親との離婚を経て、シングルファーザーとして育ててきた。
術後、娘に電話でこう伝えたという。
「父ちゃん、足なくなったけど、生きてるよ」
その声の向こうで、娘が静かに「よかった」と呟いた。
たった一言が、二郎の心に火を灯した。
彼のリハビリの原動力は、舞台でも拍手でもない。
「もう一度、娘に笑われたい」
その思いだけが、義足を支える力になっている。
■ “義足の漫才師”としての未来
有吉弘行をはじめ、芸人仲間は口を揃えて言う。
「二郎さんは、また舞台に戻る」
もしかすると、次に彼が舞台に立つとき、
そこに立っているのは――“義足の漫才師”だ。
舞台袖には、人工透析の痕。
マイクスタンドの横には、鉄の足。
それでも彼は、観客を見渡し、
最初にこう言うだろう。
「どうもー! 生き返り芸人、ハチミツ二郎です!」
きっとその瞬間、笑いと涙が交錯する。
彼がずっと守ってきた“命の笑い”が、再び会場を包む。

「足がなくても、ステージは歩けるブー…。
だって、心の中には“無限のマイクスタンド”が立ってるブー!」
ハチミツ二郎の物語は、単なる闘病記ではない。
それは、“生きる”という芸を全うする男の記録だ。
切断も、透析も、敗血症も――すべては「笑い」に変えるための伏線。
彼が義足を履いて再びマイクの前に立つ日、
そのステージは、人生そのもののリハビリになるだろう。
生きて、笑う。
それが、ハチミツ二郎の芸であり、哲学だ。




















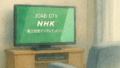









コメント