「創業百年、秘伝のタレを継ぎ足し続けています」
うなぎ屋や焼き鳥店の暖簾に誇らしげに掲げられるこの言葉。
でも、ふと立ち止まって考えてみたことはないだろうか?
え、それって…腐らないの?
ていうか、なんか気持ち悪くない?
この素朴すぎる疑問を、芸人・岡野陽一さんがテレビで口にしたことで、
あらためて「秘伝のタレの安全性」や「継ぎ足し文化」の仕組みに注目が集まった。
“気持ち悪い”と思ったその先に、
「火」「人」「時間」が守り続ける奇跡の液体の正体がある──
今回は、そんな秘伝のタレに秘められた科学と文化の深層を、あらためて掘り下げていく。
第1章:岡野陽一の素朴な疑問──「あれ、気持ち悪くないですか?」
芸人・岡野陽一さんがバラエティ番組でこう語った。
「秘伝のタレって、冷静に考えたら気持ち悪くないですか?」
ウナギ屋や焼き鳥店の暖簾に誇らしげに書かれた「創業○○年 継ぎ足しのタレ」。
美味しさの象徴のように語られてきたこの文句に、岡野さんは静かに疑問を呈したのだ。
──確かに、冷静に考えてみればちょっと不思議だ。
- 食べ物は時間が経てば腐るはず
- 冷蔵保存でもないのに、常温で長年継ぎ足し
- もしかして“菌”とか“大丈夫なの?”
こうした素朴な問いが、実は多くの人の心の中に引っかかっていた。
では、なぜタレは腐らないのか?
そしてその“気持ち悪さ”を超えて、どんな科学と文化があるのか?
第2章:実は“毎回ちょっと殺菌してる”──継ぎ足しタレの科学的メカニズム
秘伝のタレは、なぜ腐らないのか?
結論から言えば──
「腐らないような運用が自然とできている」からである。
■ カギは“低温殺菌状態”にあった
例えば、ウナギの蒲焼や焼き鳥の店では…
- 焼きたての高温の串や身を、そのままタレ壺にドボン
- 肉や魚の表面は80℃以上、中心部も60〜70℃程度
- その熱がタレ全体に伝わり、容器内の温度が60℃以上をキープ
- 結果、微生物が死滅する“低温殺菌状態”が自然に生まれている
いわば、タレは“客足が途切れない限り、毎日じわじわと熱殺菌されている”というわけだ。
■ なぜ「一度に加熱」しないのか?
タレの安全を考えるなら、一度加熱して沸騰させた方が良いのでは?
──と思うかもしれない。が、それでは味が壊れてしまう。
- タレにはタンパク質や糖分、酵母などの複雑な成分が含まれている
- 一度に高温加熱すると、風味が飛び、焦げやえぐみの原因にもなる
- “じわじわと熱が加わる”自然な低温殺菌が、味と安全性の両立に最適
名店のタレほど「火入れのリズム」に気を使っているのはこのためだ。
第3章:「名店ほど腐らない」のはなぜ?──“客が殺菌している”という事実
「秘伝のタレは腐らない」と言っても、どんな店でもそうとは限らない。
むしろ、“名店だからこそ腐らない”のだ。
いったい、その差はどこにあるのか?
■ ポイントは「客の数」と「頻度」
- 客が多ければ多いほど、焼きたての串がタレに浸かる回数が増える
- つまり、加熱された食材が頻繁にタレ壺に“熱投入”される
- タレの温度は下がらず、常時60℃前後をキープできる
- さらに“継ぎ足し”が頻繁なので、酸素も入りにくく、腐敗菌も定着しづらい
人気店=タレが常に熱と循環で活性化している状態なのだ。
■ 逆に、暇な店は…?
- 串があまり浸からない
- タレの温度が下がる
- 空気に触れる時間が長くなる
- 腐敗菌が定着しやすくなる
つまり、タレを腐らせる最大の敵は「雑菌」ではなく、“暇”なのである。
タレを守るのは、厨房でもなく冷蔵庫でもない。
毎日足を運ぶ“客”こそが、無意識にタレを守っていたのだ。
第4章:「腐らせない」ではなく「育てている」──継ぎ足し文化の哲学
秘伝のタレは単なる保存物ではない。
それは、長年の“食の継承”そのものだ。
■ “腐る”のではなく、“育つ”
- タレは、日々焼きたての旨味を吸い込んで熟成していく
- 甘み、塩気、コク、焦げの香ばしさが折り重なっていく
- 結果、「今日より明日、明日より来年」の味わいが生まれる
つまり、秘伝のタレとは“旨味の堆積でできた地層”のようなもの。
それは、ただの液体ではない。時間を味わう調味料なのだ。
■ 「気持ち悪い」は、“知る”ことで超えられる
たしかに、冷静に考えれば少し怖い。
- 何十年も継ぎ足されている
- 何が入っているかわからない
- 同じ容器で、洗ってすらいない?
でもそこには、科学的な殺菌状態と、味の進化の物語がある。
「気持ち悪い」という感情は、
知らなかったものに出会ったときの“防衛本能”でもある。
だからこそ、知れば超えられる。
秘伝のタレは、「気持ち悪さ」の向こうにある“旨さと物語”への入り口なのだ。
第5章:タレは語る──火と人と時間がつくる“奇跡の液体”
創業〇〇年、継ぎ足しのタレ。
それはただの調味料ではない。火と人と時間によって守られてきた“液体の文化財”である。
■ 火が雑菌を寄せつけず〜
- 火が雑菌を寄せつけず
- 人が手を抜かず継ぎ足し
- 時間が旨みを積み重ねる
この三つが揃って、初めてタレは腐らずに生き続ける。
それは、料理という営みが「科学」と「信仰」と「日々の積み重ね」でできていることの証明でもある。
まとめ:秘伝のタレが腐らない理由は、文化が腐らないから
- 毎日の火入れで自然な低温殺菌が保たれる
- タレは味だけでなく“循環と歴史”を吸い込んで熟成する
- 人気店ほどタレが腐らないのは、客が絶えないから
- “気持ち悪さ”は知識と理解によって越えられる
- タレが腐らないのは、厨房で人と火と食材が生きている証拠

「タレは腐らないんじゃない、“生きてる”んだブー!」
「味だけじゃない、文化の火種がそこに残ってるんだブー…」





















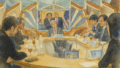
コメント