秋が深まり、果物売り場が豊かな色彩に染まる季節。その一角で、艶やかなオレンジ色の輝きを放つ「柿」。上品な甘さと、とろりとした食感は、多くの日本人にとって、秋の訪れを告げる、懐かしくも愛おしい味覚である。
しかし、不思議なことに、その圧倒的な存在感は、お菓子売り場に足を踏み入れた途端、忽然と薄れてしまうのである。
秋のお菓子コーナーは、「栗(マロン)」や「さつまいも」、「かぼちゃ」といったスター選手たちが、チョコレートからクッキー、アイスクリームに至るまで、華々しいコラボレーション商品を展開する独壇場だ。その中で、「柿味」の新商品を見かける機会は、驚くほど少ない。
なぜ、これほどまでに愛されている果物でありながら、お菓子の世界では、柿は主役の座に就けないのか。
本稿は、この素朴な疑問の裏に隠された、科学的、経済的、そして文化的ないくつかの「壁」を、一つ一つ丁寧に解き明かしていくものである。
第一章:【化学の壁】加工を阻む、柿の“繊細すぎる”化学的性質
柿がお菓子の原料として扱いにくい、最も根本的な理由。それは、柿という果物が持つ、極めて繊細で、そして厄介な化学的性質にある。
- 【風味の問題】あまりに繊細で、熱に弱い“はかない香り”
- 私たちが柿に感じる美味しさとは、暴力的な甘さではない。どこか和の趣を感じさせる、上品で、奥ゆかしく、そして繊細な甘さと香りである。
- しかし、お菓子として加工する過程では、多くの場合、加熱殺菌や乾燥、濃縮といった工程が不可欠だ。柿の繊細な風味成分は、この「熱」に非常に弱いという致命的な弱点を持つ。加熱することで、その特徴的な香りが飛んでしまい、ただぼんやりと甘いだけの、個性のない風味になってしまうのだ。
- イチゴやレモンのように、加熱しても力強い香りを保ち続ける果物とは、根本的な性質が異なる。柿の風味は、ロックバンドではなく、静かな弦楽四重奏のようなもの。工場の大きな機械音の中では、その美しい旋律はかき消されてしまうのである。
- 【渋みの問題】最大の難敵、「タンニン」という名の時限爆弾
- これが、柿の加工における最大の壁だ。柿には、ポリフェノールの一種である「タンニン」が豊富に含まれている。これが、未熟な柿を食べた時に感じる、口の中がギュッとなるような強烈な「渋み」の正体である。
- 甘柿は、成熟するとタンニンが不溶化(水に溶けなくなり、渋みを感じなくなる)するため、生で美味しく食べられる。しかし、加工のためにすり潰したり、加熱したりすると、この不溶化したタンニンが、再び水に溶け出して渋みを感じさせてしまう「渋戻り」という、悪夢のような現象が起きることがある。
- この渋みを完全に取り除くには、アルコールや炭酸ガスを使った「渋抜き」という工程が必要だが、これは非常に手間とコストがかかる。お菓子の原料として、安定した品質を大量に確保するには、この「渋み」という時限爆弾は、あまりにもリスクが高すぎるのだ。
- 【変色の問題】すぐに茶色くなる、見た目の課題
- 柿の果肉は、リンゴやバナナと同じように、空気に触れるとすぐに茶色く変色してしまう。美しいオレンジ色を保ったまま加工するには、変色を抑えるための添加物が必要となり、これもまたコストと手間を増加させる要因となる。
第二章:【物理の壁】原料としての扱いにくさと、完成されすぎた“絶対王者”
化学的な性質に加え、柿は物理的にも、お菓子の原料として扱いやすい果物とは言えない。
- 高い水分量と、繊維質な食感
- 柿は非常に水分量が多く、ジューシーな果物だ。これを、クッキーやチョコレートに混ぜ込めるような、安定したパウダーやペースト状に加工するのは、多大なエネルギーとコストがかかる。
- また、その独特の繊維質な食感は、生のまま食べる際には魅力となるが、滑らかなクリームやチョコレートと混ぜ合わせる際には、均一性を損なう要因となり得る。
- 「干し柿」という、完成されすぎた“絶対王者”
- 「柿の加工品」と聞いて、日本人が真っ先に思い浮かべるのは「干し柿」だろう。干し柿は、乾燥させることで渋みが抜け、甘みが凝縮されるという、先人たちが生み出した完璧な加工方法である。
- しかし、この干し柿の濃厚な甘さと、ねっとりとした食感は、あまりにも個性が強すぎる。これをさらに別のお菓子に展開しようとすると、その個性が他の素材と衝突してしまいがちだ。干し柿は、それ自体が一つの完成された「お菓子」であるため、他の製品の「原料」としては、むしろ使いにくい存在なのである。
第三章:【市場の壁】秋の味覚、仁義なき戦い──強力すぎるライバルたちの存在
仮に、技術的な問題を全てクリアできたとしても、「柿味」のお菓子は、お菓子売り場という厳しい戦場で、強力すぎるライバルたちと戦わなければならない。
秋の味覚の「三強」といえば、「栗(マロン)」「さつまいも」「かぼちゃ」である。
なぜ、これらは、お菓子の世界でこれほどまでに愛されるのだろうか。
| 秋の味覚 | お菓子としての強み | 柿との比較 |
|---|---|---|
| 栗(マロン) | ・「モンブラン」に代表される、洋菓子との圧倒的な親和性。 ・濃厚で、加熱しても風味が損なわれにくい。 ・ペースト状に加工しやすく、高級感のあるイメージ。 | 柿には、マロンのような「洋のイメージ」が弱く、風味も加熱に弱い。 |
| さつまいも | ・「焼きいも」を思わせる、甘く香ばしい風味。 ・でんぷん質が豊富で、お菓子に「ほっくり」とした食感を与えられる。 ・スイートポテトや大学芋など、お菓子としての歴史が長い。 | 柿はでんぷん質が少なく、お菓子の食感をコントロールしにくい。 |
| かぼちゃ | ・独特の甘みと、鮮やかなオレンジ色が、見た目にも魅力的。 ・「パンプキンパイ」など、特にハロウィンの時期に絶大なブランド力を持つ。 ・ペースト状にしやすく、様々なスイーツに応用可能。 | 柿のオレンジ色も美しいが、かぼちゃほど強いブランドイメージと結びついていない。 |
このように、秋のお菓子市場は、すでに強力なプレーヤーによって、そのポジションが確立されている。柿がこの牙城に割って入るためには、よほど革新的な商品でなければ、消費者の心をつかむのは難しいのである。

「確かに!秋になると、コンビニにはマロンと芋とカボチャのお菓子ばっかり並ぶんだブー!柿の出る幕が、なかなかないんだブーね…!頑張れ、柿なんだブー!」
第四章:【文化の壁】「生で食べるのが一番美味しい」という、私たちの“共通認識”
最後に、私たち消費者の側に根付いた、文化的な認識も、この問題に影響を与えている。
- 柿は「そのまま食べる」のが至高、という文化
- 多くの日本人にとって、柿は、皮をむいて、そのまま、あるいはせいぜいサラダや白和えに入れる程度で、「生で味わう」のが最も美味しいという、強い共通認識がある。
- イチゴであれば「ショートケーキ」を、リンゴであれば「アップルパイ」を連想するように、柿には、多くの人が共有する「柿を使った代表的なお菓子」が存在しない。
- この「生食文化」が根強いがゆえに、メーカー側も「わざわざ加工しなくても、生で十分に需要がある」と判断し、新たな加工品開発へのモチベーションが上がりにくい、という側面があるのだ。
- どこか懐かしい、「和」のイメージ
- 柿という果物には、どこか「おばあちゃんの家」「田舎の風景」といった、ノスタルジックで、穏やかな「和」のイメージがつきまとう。このイメージは、決して悪いものではないが、コンビニやスーパーで次々と発売される、目新しさや刺激を求める現代のお菓子市場のトレンドとは、少し距離があるのかもしれない。
終章:希少だからこそ価値がある──秋だけがくれる、特別な贈り物
「なぜ、柿味のお菓子は少ないのか?」
その答えは、単一のものではなかった。
- 化学の壁: 繊細で熱に弱い「風味」と、暴れ出す「渋み」。
- 物理の壁: 加工しにくい「水分量」と、完成されすぎた「干し柿」。
- 市場の壁: 強力すぎる「栗・芋・かぼちゃ」というライバルたち。
- 文化の壁: 「生で食べるのが一番」という、私たちの共通認識。
これらの幾重にも重なる壁が、柿がお菓子の世界の主役になるのを、阻んでいるのである。
しかし、見方を変えれば、これは柿という果物が持つ、素晴らしい個性そのものを物語っているのかもしれない。
お菓子として大量生産・大量消費される道を選ばず、秋という限られた季節にだけ、その繊細で、ありのままの姿で、私たちの前に現れる。その希少性こそが、柿という果物の、最大の価値なのではないだろうか。
今年もまた、秋が深まれば、柿は店先に並ぶ。
お菓子売り場にその姿は少なくとも、私たちは、皮をむけば、いつでもあの甘美な味に出会うことができる。それは、日本の秋が私たちにくれる、何物にも代えがたい、特別な贈り物なのである。

「そっかぁ…。お菓子になりにくいのは、柿が柿らしくあるための、証拠みたいなものなんだブーね!無理してお菓子にならなくても、生のままで最高においしいんだから、それでいいんだブー!今年も、生の柿をいっぱい食べるんだブー!」





















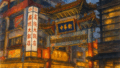
コメント