天気予報の「雨」のところに、当たり前のように並んでいる☂傘マーク。私たちは何の疑問もなく受け入れているが、実は世界の天気予報を見渡すと、主流は「雲+雨粒」のアイコンであり、「傘」を前面に出す国は意外なほど少ない。
なぜ日本の天気予報では、雨を「雲」ではなく「傘」で表現するのか? そして、その傘マーク誕生のカギを握っていたのが、まさかの“あの偉人”だとしたら──。
本稿では、天気予報アイコンの歴史をひもときながら、日本独自の「傘マーク」が生まれた背景と、その裏に潜む“傘文化”と“防災意識”を深掘りしていく。
第一章:世界の雨マークは「雲+雨粒」──日本の“傘マーク”は少数派だった
まずは、「雨=傘マーク」がどれくらい“普通”なのか、世界の天気予報と比較してみよう。
- 欧米・アジアの多く: 雨は「雲+雨粒」で表現されるのが主流。
- 日本: TV・新聞・アプリなどで、いまだに「傘」単体、もしくは「傘+雨粒」が頻出。
- 日本の大学の広報などでも: 「世界では雲+雨粒が主流だが、日本では傘マークが使われている」と“日本ならではのアイコン”として紹介されている。
つまり、私たちが「雨といえば傘マーク」と当たり前に思っている感覚は、世界基準で見るとかなり“日本ローカル仕様”だと言える。
では、この「傘マーク」は、いつ、どのようにして“雨の顔”として定着していったのだろうか。
第二章:傘マーク誕生の鍵は“福沢諭吉”──『時事新報』が描いたイラスト天気予報
傘マークのルーツをたどると、意外な人物に行き着く。そう、1万円札(旧)でもおなじみの福沢諭吉である。
- 福沢諭吉と『時事新報』: 福沢が創刊した新聞『時事新報』は、明治期に「イラスト入り天気予報」を掲載したことで知られる。
- 1890年代の紙面: 1893(明治26)年前後の紙面には、天気予報の欄に晴れ=太陽と日傘、雨=雨傘を差した人といったイラストが描かれていたとされる。
- 「文字だけ」から「絵で伝える」へ: 文字が読めない人にも直感的に伝わるよう、天気を絵で表したこの試みは、専門家から「日本の天気マークの原点」とも位置づけられている。
つまり、日本で「天気をアイコンで伝える」という発想が最初に形になったときから、すでに「雨=傘」の構図が含まれていたわけだ。
ここで重要なのは、福沢が選んだのが「雲」ではなく「傘」だった点である。空の状態(雲)ではなく、人間の行動(傘を差す)を描くことで、「あなたの生活にどんな影響が出るか」を視覚的に伝えようとしていたとも解釈できる。

「まさか天気予報の“傘マーク”のルーツに、福沢諭吉が関わっていたなんて…! お札の人が、天気アイコンにも影響してたなんて、歴史のつながりって面白いんだブー!」
第三章:テレビ時代に“☂”が全国区に──昭和の天気予報で定着した日本流
新聞で始まった「イラスト天気予報」は、やがてテレビの時代を迎えることで、さらに多くの人の目に触れるようになる。
- テレビ普及とともに: 昭和40年代以降、テレビの天気予報が全国に普及。そこで使われ始めたのが、現在もおなじみの「晴れ・曇り・雨・雪」の基本アイコンだった。
- 雨=傘マークの登場: 雨のマークとして、雲から降る雨粒ではなく、「傘」あるいは「傘+雨」のデザインが多く採用されていく。明確な“初出年”は特定しづらいものの、「テレビ天気予報の黎明期〜普及期」に傘マークが広がったとされる。
- 「生活行動を示す天気」へ: 空の状態だけでなく、「傘を持つべきかどうか」がひと目でわかるアイコンは、視聴者にとって極めて実用的だった。
こうして、「雨の日のアイコン=傘」という構図は、テレビとともに日本全国へ浸透していった。
その裏側には、日本特有の「傘文化」の影響も見え隠れする。ビニール傘の普及、駅やコンビニの傘立て、置き傘の習慣──。
突然の雨にも即座に対応しようとする国民性が、「傘」を雨の象徴として受け入れやすくしたのかもしれない。
第四章:「雨が少しでも降るなら傘マーク」──気象庁のロジック
では、現代の公式な天気予報では、「傘マーク」はどのような考え方で使われているのだろうか。
気象庁の天気予報マークに関する説明を読むと、「雨や雪が降る場合は、優先してそのマークを表示する」と明記されている。たとえ「夜遅くから雨」であっても、対象日のどこかで雨が見込まれるなら、“情報として重要”と判断して雨(傘)マークがつく、という考え方だ。
- 空模様より「雨が降るかどうか」が最優先: 晴れ・曇りの時間が長くても、どこかで雨が降るなら「雨マーク」を前面に出す。
- 生活への影響を重視: 傘が必要になるかどうかは、通勤・通学・外出計画に直結するため、予報アイコン上も最優先で示される。
- 詳細は文章で補完: アイコンだけでは表現しきれない時間変化は、天気予報文や時系列予報で補う、という役割分担になっている。
ここでもやはり、「空の様子」そのものよりも、「人がどんな行動をとるべきか」を優先していることがわかる。
空の絵ではなく、行動の象徴としての“傘”が選ばれているのは、その象徴的な表れと言えるだろう。

「“雲が出るかどうか”より、“傘がいるかどうか”の方が大事っていう発想なんだブーね。そう考えると、傘マークってけっこう実務的で、日本らしい合理性があるんだブー。」
終章:傘マークは「空」ではなく「わたしたちの生活」を映すアイコン
天気予報で雨が傘マークなのは、単なるデザイン上の偶然ではない。
福沢諭吉の新聞『時事新報』が、文字よりも「絵」で天気を伝えようとした時代から、日本の天気情報は一貫して、「空の状態」以上に「人がどう備えるべきか」を重視してきた。
世界の多くが「雲+雨粒」で空模様を描くなか、日本はあえて「傘」という“生活道具”を前面に押し出した。そこには、突然の雨にもきちんと備えようとする、日本ならではの傘文化と、防災意識の高さがにじんでいるのかもしれない。
次に天気予報で傘マークを見かけたとき、私たちはこう考えてみてもいい。「あの小さなアイコンは、空の絵ではなく、自分たちの暮らし方の“記号”なんだ」と。
たかが傘マーク。されど傘マーク。 その一滴のようなデザインの裏側には、日本のメディア史と、生活者へのまなざしが、静かに折りたたまれている。




















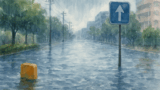

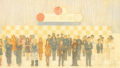
コメント